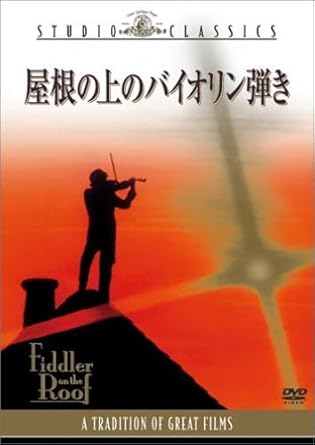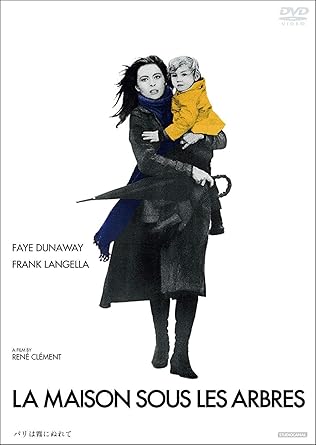外国映画レビュー──1971年
製作国:イタリア・フランス
日本公開:1971年10月23日
監督:ルキノ・ヴィスコンティ 製作:ルキノ・ヴィスコンティ 脚本:ルキノ・ヴィスコンティ、ニコラ・バダルッコ 撮影:パスクァリーノ・デ・サンティス 音楽:グスタフ・マーラー
キネマ旬報:1位
ヴェネツィアの美しい映像だけでも観る価値がある
トーマス・マンが1912年に書いた同名小説が原作。主人公の作家が映画では作曲家に変更され、マーラーを模しているとされる。ダーク・ボガードの容貌もマーラーに似ていて(ただし、晩年には髭はない)、全編に渡ってマーラーの交響曲5番第4楽章アダージェットが使用されている。マーラーは47歳の時に長女を5歳で亡くし、51歳で敗血症のためにウィーンで死んでいる。映画中で主人公と美学論争をする相手はシェーンベルクだとされる。
映画のテーマは美で、このような観念的映画は観る人によって評価は異なる。一般的な映画ファンの観方をすれば、避暑地のホテルで美少年に恋した老作曲家が疫病に掛かって客死する話であり、少年の美しさと美しいヴェネツィアの風景、絢爛たるホテルに魅了されるか、あるいはそれを退廃的、退屈と感じるかになる。
テーマに即するなら、老作曲家が平凡であるがゆえに美を見い出せないと悩み、静養先のホテルで見かけた少年に理想的な美を見い出す。その美は疫病の恐怖に勝り、老作曲家は疫病に罹患してなお、化粧による美を求め、少年を美の対象として眺めることに満足して斃れる。少年は美に囚われた彼を蝕む疫病そのものであり、主人公はその疫病に染まることで初めて美を見い出す。死と引き換えに美を手に入れた主人公、これが観念的解釈。
ヴィスコンティの映像は美しい。主観と客観の視点を織り交ぜた長回しのパンとズームで映し出されるシーンは、観る者を引きこむ絢爛で耽美な絵巻物。モブシーンではエキストラひとりひとりに至るまで完璧に計算された演技が付けられていて、黒澤明の完全主義とは違ったヴィスコンティの美と映像に対する完璧主義を見ることができる。物語もたゆたうように静かに流れるが、長回しの映像とゆったりとした音楽による描写によって観る者の心理は主人公に同一化され、決して退屈させない。そのヴィスコンティの耽美的映像魔術に酔うという楽しみ方もあって、これは映画芸術的な観方。
付け加えれば、テレビ的な細かいカットで繋ぐのを良しとする昨今の映画は、この作品に多くを学ぶことができる。原題は"Death in Venice"(ベニスでの死)で、『ベニスに死す』は作品のイメージからはかっこ良すぎる。また疫病のコレラは下痢と脱水症状を伴うが、映画の描写はむしろペストのようで違和感を感じる。コレラの症状はヴィスコンティの美学に合わなかったということか? (評価:4.5)

日本公開:1971年10月23日
監督:ルキノ・ヴィスコンティ 製作:ルキノ・ヴィスコンティ 脚本:ルキノ・ヴィスコンティ、ニコラ・バダルッコ 撮影:パスクァリーノ・デ・サンティス 音楽:グスタフ・マーラー
キネマ旬報:1位
トーマス・マンが1912年に書いた同名小説が原作。主人公の作家が映画では作曲家に変更され、マーラーを模しているとされる。ダーク・ボガードの容貌もマーラーに似ていて(ただし、晩年には髭はない)、全編に渡ってマーラーの交響曲5番第4楽章アダージェットが使用されている。マーラーは47歳の時に長女を5歳で亡くし、51歳で敗血症のためにウィーンで死んでいる。映画中で主人公と美学論争をする相手はシェーンベルクだとされる。
映画のテーマは美で、このような観念的映画は観る人によって評価は異なる。一般的な映画ファンの観方をすれば、避暑地のホテルで美少年に恋した老作曲家が疫病に掛かって客死する話であり、少年の美しさと美しいヴェネツィアの風景、絢爛たるホテルに魅了されるか、あるいはそれを退廃的、退屈と感じるかになる。
テーマに即するなら、老作曲家が平凡であるがゆえに美を見い出せないと悩み、静養先のホテルで見かけた少年に理想的な美を見い出す。その美は疫病の恐怖に勝り、老作曲家は疫病に罹患してなお、化粧による美を求め、少年を美の対象として眺めることに満足して斃れる。少年は美に囚われた彼を蝕む疫病そのものであり、主人公はその疫病に染まることで初めて美を見い出す。死と引き換えに美を手に入れた主人公、これが観念的解釈。
ヴィスコンティの映像は美しい。主観と客観の視点を織り交ぜた長回しのパンとズームで映し出されるシーンは、観る者を引きこむ絢爛で耽美な絵巻物。モブシーンではエキストラひとりひとりに至るまで完璧に計算された演技が付けられていて、黒澤明の完全主義とは違ったヴィスコンティの美と映像に対する完璧主義を見ることができる。物語もたゆたうように静かに流れるが、長回しの映像とゆったりとした音楽による描写によって観る者の心理は主人公に同一化され、決して退屈させない。そのヴィスコンティの耽美的映像魔術に酔うという楽しみ方もあって、これは映画芸術的な観方。
付け加えれば、テレビ的な細かいカットで繋ぐのを良しとする昨今の映画は、この作品に多くを学ぶことができる。原題は"Death in Venice"(ベニスでの死)で、『ベニスに死す』は作品のイメージからはかっこ良すぎる。また疫病のコレラは下痢と脱水症状を伴うが、映画の描写はむしろペストのようで違和感を感じる。コレラの症状はヴィスコンティの美学に合わなかったということか? (評価:4.5)

製作国:イギリス、アメリカ
日本公開:1972年4月29日
監督:スタンリー・キューブリック 製作:スタンリー・キューブリック 脚本:スタンリー・キューブリック 撮影:ジョン・オルコット 音楽:ウォルター・カーロス
キネマ旬報:4位
人間の暴力性を描くシュールリアリズムの名作
アンソニー・バージェスの同名小説が原作。原題は"A Clockwork Orange"。
舞台は近未来のロンドンで、美術・撮影・演出ともにシュールな世界が展開する前衛的映画。シュールで前衛的映画というと作り手の意欲ばかりが先走った失敗作が多く、公開時は私自身もこの前衛さについていけなかった気がする。しかし見直してみると、現在の意欲作に少しも引けを取らず、というよりは遥かな高みにあり、キューブリックの映画作りは何十年も先を行っていたこと、その完成度の高さに驚かされる。
内容的は人間に内在する暴力、欺瞞、非人間性を風刺的に描いているが、悪魔的な主人公の人間性の唯一の証となっているのがベートーベンの音楽で、全編にクラッシック音楽が効果的に使われている。
他の作品にも共通するキューブリックの斬新で様式的なカメラワークのオンパレードも見どころ。 (評価:3.5)

日本公開:1972年4月29日
監督:スタンリー・キューブリック 製作:スタンリー・キューブリック 脚本:スタンリー・キューブリック 撮影:ジョン・オルコット 音楽:ウォルター・カーロス
キネマ旬報:4位
アンソニー・バージェスの同名小説が原作。原題は"A Clockwork Orange"。
舞台は近未来のロンドンで、美術・撮影・演出ともにシュールな世界が展開する前衛的映画。シュールで前衛的映画というと作り手の意欲ばかりが先走った失敗作が多く、公開時は私自身もこの前衛さについていけなかった気がする。しかし見直してみると、現在の意欲作に少しも引けを取らず、というよりは遥かな高みにあり、キューブリックの映画作りは何十年も先を行っていたこと、その完成度の高さに驚かされる。
内容的は人間に内在する暴力、欺瞞、非人間性を風刺的に描いているが、悪魔的な主人公の人間性の唯一の証となっているのがベートーベンの音楽で、全編にクラッシック音楽が効果的に使われている。
他の作品にも共通するキューブリックの斬新で様式的なカメラワークのオンパレードも見どころ。 (評価:3.5)

製作国:アメリカ
日本公開:1973年1月13日
監督: スティーヴン・スピルバーグ 製作:ジョージ・エクスタイン 脚本:リチャード・マシスン 撮影:ジャック・A・マータ 音楽:ビリー・ゴールデンバーグ
キネマ旬報:8位
作品はテレビサイズだが、それを凌ぐものがある
スピルバーグが映画監督となるきっかけとなった作品。テレビ映画として作られたが評判を呼び、日本では劇場公開された。リチャード・マシスンの同名の短編小説が原作。原題は"Duel"で、決闘の意。
一番強烈な印象を残したのは踏切のシーンで、『激突!』といえば真っ先にこれが思い浮かぶ。物語は至って単純で、仕事先に向かうセールスマンの乗った車がハイウェーでディーゼル・トラックを追い越したために執拗な嫌がらせを受け、ストーカーとなったトラックに命を狙われる。トラックの運転手の顔が見えず、現代社会の恐怖として描かれた。
本作は単純にその恐怖のみを描くが、着想のユニークさと迫力ある演出と映像によって高く評価された。ただスピルバーグ以外のスタッフは二流で、シナリオの説明的なモノローグが余計で音楽もコンセプトがなくひどい。(但し、モノローグは劇場公開時にはなく、ビデオで加えられたらしい)
俳優の演技も今ひとつで映画として観ると安っぽい。カメラもスタンダード・サイズで、シネスコならもっと迫力ある映像が見られた。
ストーリー的には、急いでいたはずなのに途中からはすっかりそのことを忘れて食事したりスクールバスを助けたりと、突っ込みどころは多いが、それも単調にならないための工夫。作品はテレビサイズだが、それを凌ぐものが本作にはある。 (評価:3)

日本公開:1973年1月13日
監督: スティーヴン・スピルバーグ 製作:ジョージ・エクスタイン 脚本:リチャード・マシスン 撮影:ジャック・A・マータ 音楽:ビリー・ゴールデンバーグ
キネマ旬報:8位
スピルバーグが映画監督となるきっかけとなった作品。テレビ映画として作られたが評判を呼び、日本では劇場公開された。リチャード・マシスンの同名の短編小説が原作。原題は"Duel"で、決闘の意。
一番強烈な印象を残したのは踏切のシーンで、『激突!』といえば真っ先にこれが思い浮かぶ。物語は至って単純で、仕事先に向かうセールスマンの乗った車がハイウェーでディーゼル・トラックを追い越したために執拗な嫌がらせを受け、ストーカーとなったトラックに命を狙われる。トラックの運転手の顔が見えず、現代社会の恐怖として描かれた。
本作は単純にその恐怖のみを描くが、着想のユニークさと迫力ある演出と映像によって高く評価された。ただスピルバーグ以外のスタッフは二流で、シナリオの説明的なモノローグが余計で音楽もコンセプトがなくひどい。(但し、モノローグは劇場公開時にはなく、ビデオで加えられたらしい)
俳優の演技も今ひとつで映画として観ると安っぽい。カメラもスタンダード・サイズで、シネスコならもっと迫力ある映像が見られた。
ストーリー的には、急いでいたはずなのに途中からはすっかりそのことを忘れて食事したりスクールバスを助けたりと、突っ込みどころは多いが、それも単調にならないための工夫。作品はテレビサイズだが、それを凌ぐものが本作にはある。 (評価:3)

製作国:アメリカ
日本公開:1973年4月7日
監督:ダルトン・トランボ 製作:ブルース・キャンベル 脚本:ダルトン・トランボ 撮影:ジュールス・ブレンナー 音楽:ジェリー・フィールディング
キネマ旬報:2位
ベトナム戦争時に公開された希望のない反戦映画
原題は"Johnny Got His Gun"(ジョニーは銃を取った)で、1939年のドルトン・トランボの同名小説が原作。トランボ自身によって監督・映画化された。
第一次世界大戦で徴兵されたジョーがヨーロッパ戦線で砲撃で四肢と顔を失い、肉塊として傷病兵の研究のために生かし続けられる話。平和と民主主義に名の下に国家の犠牲となる若者たちを痛烈に皮肉った反戦小説で、トランボ自身は赤狩りで逮捕されている。タイトルは、当時志願兵募集の宣伝コピー"Johnny Get Your Gun"から取られている。
映画はベトナム戦争中に製作・公開され、ベトナム反戦映画として話題になった。公開時に映画館で見たが、再見するのは40年ぶり。重いテーマの作品だけに再見が躊躇われたが、最初のときよりも冷静に見られたのは、年齢のせいか。
本作のテーマは反戦というよりも、愛国という美名によって為政者や大人たちが未来ある若者たちの命を奪う戦争(徴兵)の裏にある、階層・世代間のエゴイズム。
生ける屍となったジョーが夢と思考の中を巡り、看護婦のMary Christmasの指文字を理解するシーンは感動的。モールス信号で意思の伝達手段を手に入れ、戦争の悲惨さを訴えようとするが、結末は悲しい。 (評価:3)

日本公開:1973年4月7日
監督:ダルトン・トランボ 製作:ブルース・キャンベル 脚本:ダルトン・トランボ 撮影:ジュールス・ブレンナー 音楽:ジェリー・フィールディング
キネマ旬報:2位
原題は"Johnny Got His Gun"(ジョニーは銃を取った)で、1939年のドルトン・トランボの同名小説が原作。トランボ自身によって監督・映画化された。
第一次世界大戦で徴兵されたジョーがヨーロッパ戦線で砲撃で四肢と顔を失い、肉塊として傷病兵の研究のために生かし続けられる話。平和と民主主義に名の下に国家の犠牲となる若者たちを痛烈に皮肉った反戦小説で、トランボ自身は赤狩りで逮捕されている。タイトルは、当時志願兵募集の宣伝コピー"Johnny Get Your Gun"から取られている。
映画はベトナム戦争中に製作・公開され、ベトナム反戦映画として話題になった。公開時に映画館で見たが、再見するのは40年ぶり。重いテーマの作品だけに再見が躊躇われたが、最初のときよりも冷静に見られたのは、年齢のせいか。
本作のテーマは反戦というよりも、愛国という美名によって為政者や大人たちが未来ある若者たちの命を奪う戦争(徴兵)の裏にある、階層・世代間のエゴイズム。
生ける屍となったジョーが夢と思考の中を巡り、看護婦のMary Christmasの指文字を理解するシーンは感動的。モールス信号で意思の伝達手段を手に入れ、戦争の悲惨さを訴えようとするが、結末は悲しい。 (評価:3)

製作国:イギリス
日本公開:1971年6月26日
監督:ワリス・フセイン 製作:デヴィッド・パットナム、デヴィッド・ヘミングス 脚本:アラン・パーカー 撮影:ピーター・サシツキー
誰かを愛するために、美少年と美少女を愛でる
公開当時、映画雑誌で主演のカップル、マーク・レスターとトレイシー・ハイドが人気となったが、この映画はこの可愛いふたりが出会って「結婚」するまでを、ビージーズのメロディに載せて観るためにある。つまりミュージック・ビデオであって、実際、映画そのものもそのように撮られている。
原題は当初"S.W.A.L.K."だった。S.W.A.L.K.は、イギリスの生徒たちがラブレターの封筒に書く文字で、"Sealed With A Loving Kiss"(愛情のキスで封をした)の略語。このタイトルではアメリカ人には意味が通じないということで、アメリカ公開時に"Melody"という原題になった。Melodyはトレーシー・ハイドが演じる少女の名前。
この映画は日本でしかヒットしなかったが、ビージーズの透明感のある曲を聴きながら、ふたりの少年少女のメルヘンを観ていると、癒された気持ちになれる。ラストは"To Love Somebody"の文字で終わるが、初恋の純粋なときめきを思い起こしてほしいということなのだろう。同じく"Love Melody xxx"の文字が最後にあるが、これも手紙の末尾に書く言葉で、xxxはキス・キス・キスを意味し、別れ際に親愛の情をこめて頬に三回キスをすることからきている。末尾の言葉の意味は「愛してるよメロディ、キス・キス・キス」で、つまり映画そのものがメロディへのラブレターとなっている。
もっとも、この映画が作られた70年頃は世界中の若者たちが既成の大人社会に異議を唱えていた時代で、同じような意味でこれは子供たちのレジスタンス映画なのかもしれない。
ロンドンが舞台だが、ティーなど庶民の生活の描写も興味深い。メロディが住む町のシーンで、唯一"Lambeth Road"の地名が登場するが、テムズ川を挟んだウエストミンスターの対岸にある。 (評価:3)

日本公開:1971年6月26日
監督:ワリス・フセイン 製作:デヴィッド・パットナム、デヴィッド・ヘミングス 脚本:アラン・パーカー 撮影:ピーター・サシツキー
公開当時、映画雑誌で主演のカップル、マーク・レスターとトレイシー・ハイドが人気となったが、この映画はこの可愛いふたりが出会って「結婚」するまでを、ビージーズのメロディに載せて観るためにある。つまりミュージック・ビデオであって、実際、映画そのものもそのように撮られている。
原題は当初"S.W.A.L.K."だった。S.W.A.L.K.は、イギリスの生徒たちがラブレターの封筒に書く文字で、"Sealed With A Loving Kiss"(愛情のキスで封をした)の略語。このタイトルではアメリカ人には意味が通じないということで、アメリカ公開時に"Melody"という原題になった。Melodyはトレーシー・ハイドが演じる少女の名前。
この映画は日本でしかヒットしなかったが、ビージーズの透明感のある曲を聴きながら、ふたりの少年少女のメルヘンを観ていると、癒された気持ちになれる。ラストは"To Love Somebody"の文字で終わるが、初恋の純粋なときめきを思い起こしてほしいということなのだろう。同じく"Love Melody xxx"の文字が最後にあるが、これも手紙の末尾に書く言葉で、xxxはキス・キス・キスを意味し、別れ際に親愛の情をこめて頬に三回キスをすることからきている。末尾の言葉の意味は「愛してるよメロディ、キス・キス・キス」で、つまり映画そのものがメロディへのラブレターとなっている。
もっとも、この映画が作られた70年頃は世界中の若者たちが既成の大人社会に異議を唱えていた時代で、同じような意味でこれは子供たちのレジスタンス映画なのかもしれない。
ロンドンが舞台だが、ティーなど庶民の生活の描写も興味深い。メロディが住む町のシーンで、唯一"Lambeth Road"の地名が登場するが、テムズ川を挟んだウエストミンスターの対岸にある。 (評価:3)

製作国:アメリカ
日本公開:1972年2月12日
監督:ウィリアム・フリードキン 製作:フィリップ・ダントニ 脚本:アーネスト・タイディマン 撮影:オーウェン・ロイズマン 音楽:ドン・エリス
キネマ旬報:10位
アカデミー作品賞 ゴールデングローブ作品賞
犯罪映画の傑作だが、すっきりしないエンディング
原題"The French Connection"で、1970年代まで存在した、トルコからフランス経由でアメリカにヘロインを密売した組織のこと。ロビン・ムーアの同名ノンフィクション小説が原作。
1961年に起きた実際の事件がモデルで、ニューヨーク市警の麻薬刑事コンビが、地道な捜査でフレンチ・コネクションを摘発する過程を描く。
なかなか尻尾を掴ませない密売組織との息詰る闘いが緊迫感たっぷりで、ジーン・ハックマン演じるポパイ刑事の執拗な追跡が見もの。とりわけ電車を車で追いかけるアクションシーンが見せ場で、ジーン・ハックマンはアカデミー主演男優賞。
対するマルセイユの麻薬卸商のボスに扮するフェルナンド・レイが、大物感があっていい。
取引に使われるロールスロイスをトコトン解体していくシーンが圧巻だが、どうやって元に戻したのかが気になるところ。
マルセイユのボスは海外逃亡しポパイ刑事も無事に終わる、ラストシーンの銃声が、何を意味しているのか不明なのが不満。
犯人たちの処遇を含め、いささかすっきりしないエンディングだが、クライム・サスペンス&アクションの往年の傑作。 (評価:2.5)

日本公開:1972年2月12日
監督:ウィリアム・フリードキン 製作:フィリップ・ダントニ 脚本:アーネスト・タイディマン 撮影:オーウェン・ロイズマン 音楽:ドン・エリス
キネマ旬報:10位
アカデミー作品賞 ゴールデングローブ作品賞
原題"The French Connection"で、1970年代まで存在した、トルコからフランス経由でアメリカにヘロインを密売した組織のこと。ロビン・ムーアの同名ノンフィクション小説が原作。
1961年に起きた実際の事件がモデルで、ニューヨーク市警の麻薬刑事コンビが、地道な捜査でフレンチ・コネクションを摘発する過程を描く。
なかなか尻尾を掴ませない密売組織との息詰る闘いが緊迫感たっぷりで、ジーン・ハックマン演じるポパイ刑事の執拗な追跡が見もの。とりわけ電車を車で追いかけるアクションシーンが見せ場で、ジーン・ハックマンはアカデミー主演男優賞。
対するマルセイユの麻薬卸商のボスに扮するフェルナンド・レイが、大物感があっていい。
取引に使われるロールスロイスをトコトン解体していくシーンが圧巻だが、どうやって元に戻したのかが気になるところ。
マルセイユのボスは海外逃亡しポパイ刑事も無事に終わる、ラストシーンの銃声が、何を意味しているのか不明なのが不満。
犯人たちの処遇を含め、いささかすっきりしないエンディングだが、クライム・サスペンス&アクションの往年の傑作。 (評価:2.5)

製作国:アメリカ
日本公開:1971年7月17日
監督:リチャード・C・サラフィアン 製作:ノーマン・スペンサー 脚本:ギレルモ・ケイン 撮影:ジョン・A・アロンゾ
キネマ旬報:5位
反体制を背負った偶像のカーアクションが半端なく爽快
原題"Vanishing Point"で、消失点の意。
アメリカン・ニューシネマの作品で、反権力と自由をテーマに、ベトナム戦争の影やヒッピー、新興宗教などの世相を織り交ぜるが、最大の楽しみどころは全編に渡って繰り広げられるカーアクションで、その爽快感は半端ではない。
主人公のコワルスキーはクルマの陸送ドライバーで、白の1970年型ダッジ・チャレンジャーをデンバーからサンフランシスコまで陸送する。
出発前にヤッたクスリがいけなかったのか、2000キロを15時間で運ぶという賭けを友人としてしまい、レース用エンジンを積んだクライスラーのこの車で疾駆する。
コロラド州で早速スピード違反で白バイに停車を命じられるが、これを振り切り、ユタ州・ネバダ州の各警察を出し抜いて暴走、カリフォルニア州に到達する。最後は前後を阻まれて行き場を失い、路上の大型ショベルカーに激突して死んでしまう。
このラストがコワルスキーの消滅点となるが、プロローグとエピローグが時間的には繋がっていて、本編はそれまでの出来事として描かれる。プロローグでは行き場を失ったコワルスキーが特攻をかける寸前に一瞬消えたようになっていて、ここが彼の精神的な消滅点だったのかもしれない。
人間精神の自由をスピードに、それを束縛する権力・体制を制限速度に比定して、コワルスキーはスピード違反以外の法令違反はしない。大衆は彼を自由の闘士として偶像化し逃げ切ることを望むが、体制の壁は厚く、行き場を失った偶像は消滅するしかなく、人々に失望しか残さない。
当時の反体制的な景色とテーマを語ればそういうことになるが、単純にカーアクションとして見た方が楽しめる。 (評価:2.5)

日本公開:1971年7月17日
監督:リチャード・C・サラフィアン 製作:ノーマン・スペンサー 脚本:ギレルモ・ケイン 撮影:ジョン・A・アロンゾ
キネマ旬報:5位
原題"Vanishing Point"で、消失点の意。
アメリカン・ニューシネマの作品で、反権力と自由をテーマに、ベトナム戦争の影やヒッピー、新興宗教などの世相を織り交ぜるが、最大の楽しみどころは全編に渡って繰り広げられるカーアクションで、その爽快感は半端ではない。
主人公のコワルスキーはクルマの陸送ドライバーで、白の1970年型ダッジ・チャレンジャーをデンバーからサンフランシスコまで陸送する。
出発前にヤッたクスリがいけなかったのか、2000キロを15時間で運ぶという賭けを友人としてしまい、レース用エンジンを積んだクライスラーのこの車で疾駆する。
コロラド州で早速スピード違反で白バイに停車を命じられるが、これを振り切り、ユタ州・ネバダ州の各警察を出し抜いて暴走、カリフォルニア州に到達する。最後は前後を阻まれて行き場を失い、路上の大型ショベルカーに激突して死んでしまう。
このラストがコワルスキーの消滅点となるが、プロローグとエピローグが時間的には繋がっていて、本編はそれまでの出来事として描かれる。プロローグでは行き場を失ったコワルスキーが特攻をかける寸前に一瞬消えたようになっていて、ここが彼の精神的な消滅点だったのかもしれない。
人間精神の自由をスピードに、それを束縛する権力・体制を制限速度に比定して、コワルスキーはスピード違反以外の法令違反はしない。大衆は彼を自由の闘士として偶像化し逃げ切ることを望むが、体制の壁は厚く、行き場を失った偶像は消滅するしかなく、人々に失望しか残さない。
当時の反体制的な景色とテーマを語ればそういうことになるが、単純にカーアクションとして見た方が楽しめる。 (評価:2.5)

製作国:アメリカ
日本公開:1972年7月20日
監督:ピーター・ボグダノヴィッチ 製作:スティーヴン・J・フリードマン、バート・シュナイダー 脚本:ラリー・マクマートリー、ピーター・ボグダノヴィッチ 撮影:ロバート・サーティース
キネマ旬報:1位
描かれる青春そのものが古きテキサス男同様に時代遅れ
原題"The Last Picture Show"で、最後の映画の意。ラリー・マクマートリーの同名の自伝的小説が原作。
1950年代初頭、テキサスの田舎町を舞台に青春をノスタルジックに振り返るという作品で、ハイスクール最終学年の主人公ソニーとその親友デュアンの友情物語という、よくあるパターンだが、『アメリカン・グラフィティ』『スタンドバイミー』といった、その後の類似作品の先駆け。
この町のデートスポットの映画館でのソニーとデュアンのダブルデートから始まり、ハイスクールを卒業して映画館の閉館上映をソニーとデュアンが二人で見るまでの青春の蹉跌が描かれるが、映画館閉館の理由が古きテキサス男の映画館主サムの死によるもので、旧き良きアメリカの終焉と映画館閉館に、二人の良き青春の思い出を重ね合わせるという作品になっている。
タイトルの"The Last Picture Show"は、この閉館上映のことで、一つの時代の終わりを描く映画だが、半世紀後に見ると、そこに描かれる青春もまた古き良き時代のもので、当時の若者たちの倫理観・価値観が今では大きく変貌していることに気づかされる。つまり、ここに描かれる青春そのものが、サム同様に時代遅れなのかもしれない。
この映画館で最初に上映されるのは『花嫁の父』(1950)、閉館上映は『赤い河』(1948)。
結婚までセックスはお預けという彼女と別れたソニーは、夫との愛情に満たされない人妻と不倫。デュアンは処女を捨てたがっているジェイシーとの初体験に失敗し、別れたジェイシーはソニーに魅かれてセックス。二人の友情にひびが入り、ソニーはジェイシーと駆け落ちするが失敗する。
ジェイシーが単なる気まぐれ女と気づいたソニーは、町を出て朝鮮戦争に志願したデュアンと仲直りし、Last Picture Showに行く。
サムの物語として、人妻だったために成就できなかった悲恋があり、その相手がジェイシーの母だったという隠し味もあって、シナリオは凝っている。
もっとも、ノスタルジー以外に何か残るものは特になく、本作自体が旧き良きアメリカ映画への"The Last Picture Show"といえなくもない。 (評価:2.5)

日本公開:1972年7月20日
監督:ピーター・ボグダノヴィッチ 製作:スティーヴン・J・フリードマン、バート・シュナイダー 脚本:ラリー・マクマートリー、ピーター・ボグダノヴィッチ 撮影:ロバート・サーティース
キネマ旬報:1位
原題"The Last Picture Show"で、最後の映画の意。ラリー・マクマートリーの同名の自伝的小説が原作。
1950年代初頭、テキサスの田舎町を舞台に青春をノスタルジックに振り返るという作品で、ハイスクール最終学年の主人公ソニーとその親友デュアンの友情物語という、よくあるパターンだが、『アメリカン・グラフィティ』『スタンドバイミー』といった、その後の類似作品の先駆け。
この町のデートスポットの映画館でのソニーとデュアンのダブルデートから始まり、ハイスクールを卒業して映画館の閉館上映をソニーとデュアンが二人で見るまでの青春の蹉跌が描かれるが、映画館閉館の理由が古きテキサス男の映画館主サムの死によるもので、旧き良きアメリカの終焉と映画館閉館に、二人の良き青春の思い出を重ね合わせるという作品になっている。
タイトルの"The Last Picture Show"は、この閉館上映のことで、一つの時代の終わりを描く映画だが、半世紀後に見ると、そこに描かれる青春もまた古き良き時代のもので、当時の若者たちの倫理観・価値観が今では大きく変貌していることに気づかされる。つまり、ここに描かれる青春そのものが、サム同様に時代遅れなのかもしれない。
この映画館で最初に上映されるのは『花嫁の父』(1950)、閉館上映は『赤い河』(1948)。
結婚までセックスはお預けという彼女と別れたソニーは、夫との愛情に満たされない人妻と不倫。デュアンは処女を捨てたがっているジェイシーとの初体験に失敗し、別れたジェイシーはソニーに魅かれてセックス。二人の友情にひびが入り、ソニーはジェイシーと駆け落ちするが失敗する。
ジェイシーが単なる気まぐれ女と気づいたソニーは、町を出て朝鮮戦争に志願したデュアンと仲直りし、Last Picture Showに行く。
サムの物語として、人妻だったために成就できなかった悲恋があり、その相手がジェイシーの母だったという隠し味もあって、シナリオは凝っている。
もっとも、ノスタルジー以外に何か残るものは特になく、本作自体が旧き良きアメリカ映画への"The Last Picture Show"といえなくもない。 (評価:2.5)

製作国:イタリア、フランス
日本公開:1972年5月5日
監督:ジュリアーノ・モンタルド 脚本:ジュリアーノ・モンタルド、ファブリッツィオ・オノフリ 撮影:シルヴァーノ・イッポリティ 音楽:エンニオ・モリコーネ
キネマ旬報:3位
アメリカ映画ではなくイタリア・フランス合作であるのも気になる
原題"Sacco e Vanzetti"で、サッコとヴァンゼッティの意。冤罪とされる強盗殺人事件で死刑となった容疑者二人の名。
1920年にマサチューセッツ州ブレインツリーの製靴工場で起きた事件で、逮捕されたサッコは靴職人、ヴァンゼッティは魚の行商人。共にイタリア移民で、アナキスト、第一次世界大戦の兵役拒否者であったことから、逮捕は偏見と差別、政治的謀略によるものという立場から描かれている。
ロシア革命直後、アメリカが労働運動や赤化に怯えていた時期の物語で、プロローグは司法長官や政治家によるアナキストへの弾圧など、時代背景の説明から始まる。
サッコ(リカルド・クッチョーラ)とヴァンゼッティ(ジャン・マリア・ヴォロンテ)の逮捕から判決までの裁判経過が描かれるが、検事(シリル・キューサック)による目撃証人のでっち上げから不利と見た弁護士(ミロ・オシー)が、裁判を政治化したことで移民とWASPとの対立へと発展。WASPによって構成される陪審員によって有罪となる。
判決後、アメリカやヨーロッパで起きた抗議デモ、再審請求、検察による証拠隠滅疑惑、州知事による特赦拒否、死刑確定・電気椅子による執行まで。
事件を冤罪とする立場から見れば、裁判の不当性を丁寧に描いていて、よくできた人種差別や思想弾圧の告発映画となっているが、事件の真偽は別にして、移民排斥と偏狭なナショナリズムが台頭する現代から見ても警鐘の作品となっている。
アメリカの物語をイタリア語で聴くのも違和感があって、アメリカ映画ではなくイタリアとフランスの作品であるのも気になるところ。
アメリカの反戦歌手として勇名を馳せたジョーン・バエズがエンディング曲"Here's to You"を歌っていて、価値のある死だというヴァンゼッティの言葉を基に作詞されている。
再審却下の法廷でヴァンゼッティが、この裁判がなければ無名で一生を終えたであろう自分たちが、政治弾圧を受けたアナキストとして後世に名を残すことができたことを検事と裁判官に感謝すると演説するシーンが最大の見せ場。
冤罪告発に大きく傾斜していてメッセージ性が強いために、映画としての中庸や面白みに欠けるのがやや残念なところか。 (評価:2.5)

日本公開:1972年5月5日
監督:ジュリアーノ・モンタルド 脚本:ジュリアーノ・モンタルド、ファブリッツィオ・オノフリ 撮影:シルヴァーノ・イッポリティ 音楽:エンニオ・モリコーネ
キネマ旬報:3位
原題"Sacco e Vanzetti"で、サッコとヴァンゼッティの意。冤罪とされる強盗殺人事件で死刑となった容疑者二人の名。
1920年にマサチューセッツ州ブレインツリーの製靴工場で起きた事件で、逮捕されたサッコは靴職人、ヴァンゼッティは魚の行商人。共にイタリア移民で、アナキスト、第一次世界大戦の兵役拒否者であったことから、逮捕は偏見と差別、政治的謀略によるものという立場から描かれている。
ロシア革命直後、アメリカが労働運動や赤化に怯えていた時期の物語で、プロローグは司法長官や政治家によるアナキストへの弾圧など、時代背景の説明から始まる。
サッコ(リカルド・クッチョーラ)とヴァンゼッティ(ジャン・マリア・ヴォロンテ)の逮捕から判決までの裁判経過が描かれるが、検事(シリル・キューサック)による目撃証人のでっち上げから不利と見た弁護士(ミロ・オシー)が、裁判を政治化したことで移民とWASPとの対立へと発展。WASPによって構成される陪審員によって有罪となる。
判決後、アメリカやヨーロッパで起きた抗議デモ、再審請求、検察による証拠隠滅疑惑、州知事による特赦拒否、死刑確定・電気椅子による執行まで。
事件を冤罪とする立場から見れば、裁判の不当性を丁寧に描いていて、よくできた人種差別や思想弾圧の告発映画となっているが、事件の真偽は別にして、移民排斥と偏狭なナショナリズムが台頭する現代から見ても警鐘の作品となっている。
アメリカの物語をイタリア語で聴くのも違和感があって、アメリカ映画ではなくイタリアとフランスの作品であるのも気になるところ。
アメリカの反戦歌手として勇名を馳せたジョーン・バエズがエンディング曲"Here's to You"を歌っていて、価値のある死だというヴァンゼッティの言葉を基に作詞されている。
再審却下の法廷でヴァンゼッティが、この裁判がなければ無名で一生を終えたであろう自分たちが、政治弾圧を受けたアナキストとして後世に名を残すことができたことを検事と裁判官に感謝すると演説するシーンが最大の見せ場。
冤罪告発に大きく傾斜していてメッセージ性が強いために、映画としての中庸や面白みに欠けるのがやや残念なところか。 (評価:2.5)

カンタベリー物語
日本公開:1973年2月17日
監督:ピエル・パオロ・パゾリーニ 製作:アルベルト・グリマルディ 脚本:ピエル・パオロ・パゾリーニ 撮影:トニーノ・デリ・コリ 音楽:エンニオ・モリコーネ
ベルリン映画祭金熊賞
原題"I racconti di Canterbury"で、邦題の意。チョーサーの"The Canterbury Tales"が原作。
カンタベリー大聖堂への巡礼の途中、チョーサーが泊まった宿屋で旅人たちが退屈しのぎに語った話を書き留めていくというもので、映画では「貿易商人の話」「托鉢僧の話」「料理人の話」「粉屋の話」「バースの女房の話」「家扶の話」「免罪符売りの話」「召喚吏の話」の八話が取り上げられる。
パゾリーニ自身がチョーサー役を演じ、原作に大胆な脚色・改変を加えてパゾリーニらしいオムニバスの艶笑話に仕上げている。全編を通して女も男も素っ裸のオンパレードで、牧歌的でおおらかな性をスラップスティックに謳うが、同時に保守的な性のモラルに対する挑戦ともなっていて、女性の性の男性支配や抑圧、同性愛者への偏見を戯画的に描き、70年代の性の解放、女性解放の時代性を反映した内容となっている。
性に対する屈託のなさを見ていると、イギリスが舞台ながら出演者全員がイタリア人に見えてしまうのはパゾリーニこそのなせる技。
もっとも性だけでなく下ネタ的な下品な描写も多いので、抵抗がある人は要注意。
映像的には中世の雰囲気が抜群で、モブシーンはまるで動く中世絵画を見ているよう。小道具、大道具、衣装といった美術や、ロケに使われた教会や城などの歴史建造物なども大きな見どころとなっている。
「料理人の話」のニネット・ダボリ、「貿易商人の話」のジョゼフィン・チャップリン(メイ)、ヒュー・グリフィス(ジャニュアリ)が印象的。 (評価:2.5)

製作国:アメリカ
日本公開:1972年4月29日
監督:サム・ペキンパー 製作:ダニエル・メルニック 脚本:サム・ペキンパー、デヴィッド・Z・グッドマン 撮影:ジョン・コキロン 音楽:ジェリー・フィールディング
キネマ旬報:5位
何でこんなバカ女と結婚してしまったかが不可解
原題"Straw Dogs"で邦題の意。『老子道徳経』の一節、天地不仁、以万物為芻狗(天地は不仁、万物を以って芻狗と為す)から。芻狗(すうく)は神に供える藁細工の犬のこと。ゴードン・M・ウィリアムズの"The Siege of Trencher's Farm"(トレンチャー農場の包囲)が原作。
舞台はイギリス・コーンウォールの小さな村。妻(スーザン・ジョージ)の生まれ故郷に移住した温厚なアメリカ人の宇宙数学者(ダスティン・ホフマン)が、粗野な村人たちの仕打ちに我慢を重ねた挙句、ちょっとした正義感から暴発してしまうという物語。
『ワイルドバンチ』(1969)で過激なバイオレンス描写で注目されたペキンパーが、人間に内在する暴力衝動を描いた作品として、公開当時、話題を呼んだ。
妻も呆れる、虫も殺せないような男が、知能の薄い青年(ピーター・アーン)を車で撥ねてしまい家で医者と警察を待つところに、この青年に娘を誘拐されたと信じる粗暴な父親(ピーター・ヴォーン)と村の男たちが青年の引き渡しを要求。これを拒絶して、家に立て籠もっての攻防戦となる。
窮鼠猫を噛むを地で行く非暴力男の容赦ない反撃が見もので、スローモーションを使った火掻き棒でのゴルフスイング殴打、虎挟み、最後は妻の銃撃と暴力の限りを尽くす。
知能の薄い青年と主人公が車を走らせながらの会話、
"I don't know my way home."(帰り道がわからない)
"That's okay. I don't either."(大丈夫、僕もそうさ)
が、心の奥の暴力衝動を知ってしまった人間の戸惑いを表す名セリフ。
しかし、本作を改めて観て思うのは、研究のために田舎に引っ越した夫に構ってもらえないのを不満に感じ、村の若い男たちを挑発する仕草で昔のボーイフレンド(デル・ヘニー)以下にレイプされてしまう妻の幼さで、インテリの主人公が何でこんなバカ女と結婚してしまったのかが不可解。
段取りのための性格設定とシナリオが感じられてしまうが、それにしても童顔のスーザン・ジョージが色気満点。 (評価:2.5)

日本公開:1972年4月29日
監督:サム・ペキンパー 製作:ダニエル・メルニック 脚本:サム・ペキンパー、デヴィッド・Z・グッドマン 撮影:ジョン・コキロン 音楽:ジェリー・フィールディング
キネマ旬報:5位
原題"Straw Dogs"で邦題の意。『老子道徳経』の一節、天地不仁、以万物為芻狗(天地は不仁、万物を以って芻狗と為す)から。芻狗(すうく)は神に供える藁細工の犬のこと。ゴードン・M・ウィリアムズの"The Siege of Trencher's Farm"(トレンチャー農場の包囲)が原作。
舞台はイギリス・コーンウォールの小さな村。妻(スーザン・ジョージ)の生まれ故郷に移住した温厚なアメリカ人の宇宙数学者(ダスティン・ホフマン)が、粗野な村人たちの仕打ちに我慢を重ねた挙句、ちょっとした正義感から暴発してしまうという物語。
『ワイルドバンチ』(1969)で過激なバイオレンス描写で注目されたペキンパーが、人間に内在する暴力衝動を描いた作品として、公開当時、話題を呼んだ。
妻も呆れる、虫も殺せないような男が、知能の薄い青年(ピーター・アーン)を車で撥ねてしまい家で医者と警察を待つところに、この青年に娘を誘拐されたと信じる粗暴な父親(ピーター・ヴォーン)と村の男たちが青年の引き渡しを要求。これを拒絶して、家に立て籠もっての攻防戦となる。
窮鼠猫を噛むを地で行く非暴力男の容赦ない反撃が見もので、スローモーションを使った火掻き棒でのゴルフスイング殴打、虎挟み、最後は妻の銃撃と暴力の限りを尽くす。
知能の薄い青年と主人公が車を走らせながらの会話、
"I don't know my way home."(帰り道がわからない)
"That's okay. I don't either."(大丈夫、僕もそうさ)
が、心の奥の暴力衝動を知ってしまった人間の戸惑いを表す名セリフ。
しかし、本作を改めて観て思うのは、研究のために田舎に引っ越した夫に構ってもらえないのを不満に感じ、村の若い男たちを挑発する仕草で昔のボーイフレンド(デル・ヘニー)以下にレイプされてしまう妻の幼さで、インテリの主人公が何でこんなバカ女と結婚してしまったのかが不可解。
段取りのための性格設定とシナリオが感じられてしまうが、それにしても童顔のスーザン・ジョージが色気満点。 (評価:2.5)

製作国:アメリカ
日本公開:1971年12月4日
監督:ノーマン・ジュイソン 製作:ノーマン・ジュイソン 脚本:ジョセフ・スタイン 撮影:オズワルド・モリス 音楽:ジョン・ウィリアムズ
キネマ旬報:6位
ゴールデングローブ作品賞 (ミュージカル・コメディ部門)
ユダヤの伝統と葛藤しつつ娘に理解を示す父の優しさ
原題は"Fiddler on the Roof"で、同名ブロードウェイ・ミュージカルの映画化。ウクライナの作家ショーレム・アレイヘムの短篇小説"Tevye der milkhiger"(牛乳屋テヴィエ)が原作。
19世紀末、帝政ロシア時代ウクライナのユダヤ人の村が舞台。牛乳屋の娘たちが次々とユダヤの旧習を破って結婚して行く様子を、ロシア革命の変革の空気とともに描く。長女は父が決めた結婚を拒否して自由恋愛、二女は革命家を追ってシベリアへ、三女はロシア正教徒と結婚してしまう。
伝統や戒律を守ろうと葛藤しながらも、娘たちに愛情と理解を示す優しい父を演じるトポルがいい。それでも三女の異教徒との結婚を許すことはアイデンティティの崩壊に繋がり、勘当するしかない。そんな父が、ユダヤ人迫害に遭って村を追い払われる際に、三女に「神の御加護を」と祈る姿が切ない。
冒頭より、敬虔な祈りは神には届かず、迫害と貧困によって苦しみを与えられた神に選ばれしユダヤ民族の嘆きが描かれる。バビロン捕囚から宿命づけられた悲劇は、時代の変革にも関わらず一家を再び流浪へと追い立てるが、差別される側のユダヤ人の牛乳屋が、同じユダヤ人の金持ちの肉屋を貶めるのも皮肉。
ユダヤ人の悲劇を描くことに終始して、哀愁以外に何も残さないのは、被害者意識しか描けない反戦映画に良く似ている。
タイトルは帝政ローマのユダヤ人虐殺での屋根の上のバイオリン弾きに由来。 (評価:2.5)

日本公開:1971年12月4日
監督:ノーマン・ジュイソン 製作:ノーマン・ジュイソン 脚本:ジョセフ・スタイン 撮影:オズワルド・モリス 音楽:ジョン・ウィリアムズ
キネマ旬報:6位
ゴールデングローブ作品賞 (ミュージカル・コメディ部門)
原題は"Fiddler on the Roof"で、同名ブロードウェイ・ミュージカルの映画化。ウクライナの作家ショーレム・アレイヘムの短篇小説"Tevye der milkhiger"(牛乳屋テヴィエ)が原作。
19世紀末、帝政ロシア時代ウクライナのユダヤ人の村が舞台。牛乳屋の娘たちが次々とユダヤの旧習を破って結婚して行く様子を、ロシア革命の変革の空気とともに描く。長女は父が決めた結婚を拒否して自由恋愛、二女は革命家を追ってシベリアへ、三女はロシア正教徒と結婚してしまう。
伝統や戒律を守ろうと葛藤しながらも、娘たちに愛情と理解を示す優しい父を演じるトポルがいい。それでも三女の異教徒との結婚を許すことはアイデンティティの崩壊に繋がり、勘当するしかない。そんな父が、ユダヤ人迫害に遭って村を追い払われる際に、三女に「神の御加護を」と祈る姿が切ない。
冒頭より、敬虔な祈りは神には届かず、迫害と貧困によって苦しみを与えられた神に選ばれしユダヤ民族の嘆きが描かれる。バビロン捕囚から宿命づけられた悲劇は、時代の変革にも関わらず一家を再び流浪へと追い立てるが、差別される側のユダヤ人の牛乳屋が、同じユダヤ人の金持ちの肉屋を貶めるのも皮肉。
ユダヤ人の悲劇を描くことに終始して、哀愁以外に何も残さないのは、被害者意識しか描けない反戦映画に良く似ている。
タイトルは帝政ローマのユダヤ人虐殺での屋根の上のバイオリン弾きに由来。 (評価:2.5)

ダーティハリー
日本公開:1972年2月26日
監督:ドン・シーゲル 製作:ドン・シーゲル 脚本:ハリー・ジュリアン・フィンク、R・M・フィンク、ディーン・リーズナー、ジョン・ミリアス 撮影:ブルース・サーティース 音楽:ラロ・シフリン
マカロニ・ガンマン、クリント・イーストウッドのハリウッド出世作となった刑事アクション。人気となりシリーズ5作まで作られた。原題は"Dirty Harry"。字幕では、お不潔ハリーと訳されていて迷訳に笑ってしまう。
主人公のハリー・キャラハンは熱血漢の刑事で、犯人の脅しには決して屈さない。市長や検察、サンフランシスコ市警の政治的事情などは糞喰らえで、正義を貫くためには法律も関係ない。本作では金を要求して無差別殺人を繰り返すベトナム帰還兵の狂人が相手。
違法捜査に対する犯人の人権保護と不起訴、司法取引による免責といった刑事訴訟手続に対する納得のいかない市民感情があって、本作は単純な正義感で犯人を罰するという明快・爽快さが受けた。物語中で、黙秘権・供述・弁護士についての告知をハリーが行わなかったために犯人が無罪となるが、これは1966年の連邦最高裁判決に基づいている。
本作を見て気がつくのは、犯人が公衆電話を使って刑事を振りまわすシナリオで、『ダイ・ハード3』の原型となっていること。この映画でハリーの持つ44マグナムが有名になった。 (評価:2.5)

デカメロン
日本公開:1972年5月20日
監督:ピエル・パオロ・パゾリーニ 製作:アルベルト・グリマルディ 原作:ジョヴァンニ・ボッカチオ 脚本:ピエル・パオロ・パゾリーニ 撮影:トニーノ・デリ・コリ 音楽:エンニオ・モリコーネ
原題"Il Decamerone"で、ボッカチオの同名の艶笑文学を脚色・映画化。
商人がナポリで女に騙されて肥壺に落ちた挙句に金を巻き上げられ、墓泥棒の手伝いをして棺桶に閉じ込められるも機転を利かして脱出する話。(ペルージャのアンドレウッチョ)
唖のふりをして尼僧院の下働きとなった青年が尼僧たち全員の相手をするが、院長に襲われて思わず喋ってしまい、一計を案じた院長がそれを神の奇跡として誤魔化す話。(マゼットと尼僧)
浮気の最中に亭主が帰ってきて間男を樽の中に入れるも、夫が樽を買いに来た男を連れていたためすでに売約済みと誤魔化し、夫に中を掃除させながら続きをする話。(ペロネッラ)
高利貸しの男が臨終に司祭を呼び嘘八百を並べて聖人になる話。(聖チャペレット)
若い公爵を夜中にベランダに忍び込ませた娘が翌朝情事を見つかるものの、父親が結婚させて玉の輿にさせる話。(カテリーナ)
妹を寝取った使用人が兄たちに殺すが、妹は死体を見つけて頭を鉢植えにして部屋に飾る話。(リザベッタとロレンツォ)。
魔法で昼間だけ女を馬に変えて働かせると騙した司祭が、女を裸にして尻尾をつけると言って挿入し夫に止められ、魔法を止めたから馬に変えられなかったと嘯く話。(コンパール・ピエトロ、ドンナ・ジェンマータとドン・ジャンニ)
先に死んだら残った方に死後の世界を教えると2人の男が約束し、先に死んだ義妹を寝取って放蕩していた男が夢枕に立って姦淫は大した罪ではないと神に言われたと話すと、もう一人が早速その義妹のベッドに行く話。(ティンゴッチョとメウッチョ)
これに教会の壁画を完成させる画家がサイドストーリーとして絡むが、艶笑話なので気楽に見られる。全体としては中世風の映像もよく、陽気なナポリ人を楽しめる。 (評価:2.5)

ラムの大通り
日本公開:1972年5月20日
監督:ロベール・アンリコ 製作:アラン・ポワレ 脚本:ロベール・アンリコ、トニー・レコーダー、ジャック・ペシュラル、ピエール・ペルグリ 撮影:ジャン・ボフェティ 音楽:フランソワ・ド・ルーベ
原題"Boulevard du Rhum"で、邦題の意。ジャック・ペシュラルの同名小説が原作。
1920年代、禁酒法時代のカリブ海が舞台で、"Boulevard du Rhum"はジャマイカからニューオリンズにラム酒を密輸する海上ルートの通称。
密輸業者のコーネリアス(リノ・ヴァンチュラ)がジャマイカの映画館でサイレント・スターのリンダ(ブリジット・バルドー)を見初めたことから始まるロマンチックコメディで、パナマの浜辺で偶然リンダに出会ったことから二人は恋に落ちる。
リンダを乗せた密輸船がフロリダ沖で沿岸警備隊の銃撃を受けるが、望遠鏡でリンダを見初めたイギリス海賊のハモンド(クライヴ・レヴィル)が援護して助かる。貴族のハモンドにプロポーズされたリンダは侯爵夫人の地位に目が眩み結婚。ところがコーネリアスがリンダを寝取って決闘となった間に、リンダは映画会社に連れ戻されてしまう。
コーネリアスは沿岸警備隊に収監されるが、1933年、禁酒法が廃止となって早速リンダの看板のかかった映画館に。「愛の喜びは束の間、愛の悲しみは永遠に」という台詞と共に、映画のカップルに自分とリンダを投影するコーネリアスが、客のいなくなった映画館の椅子にいつまでも座っている姿がいい。
冒頭、コーネリアスが沿岸警備隊や業者仲間と争うアクション映画と思いきや、ブリジット・バルドーの登場と共にロマンチックコメディに変身、タイトルの「ラムの大通り」は何処に行ったんだと思っていると、ラストでこの二つの話がパラレルだったことがわかるというシナリオが上手い。
コーネリアスはリンダとの良き思い出と共に、彼女が本来いるべき世界に戻ったことに安堵する。一方、禁酒法時代が終わり、アメリカ社会もまた本来あるべき姿に戻り、平安が訪れる。
悪法下で密輸業者としてカリブ海の海を駆けた冒険も、映画スターと恋に落ちたのも、束の間の夢と終り、思い出は永遠に残るという、ロマンチックなエンディングとなっている。
セーラー姿などブリジット・バルドーの衣装も見どころ。 (評価:2.5)

さすらいのカウボーイ
日本公開:1972年3月11日
監督:ピーター・フォンダ 製作:ウィリアム・ヘイワード 脚本:アラン・シャープ 撮影:ヴィルモス・ジグモンド 音楽:ブルース・ラングホーン
原題"The Hired Hand"で、使用人の意。
ピーター・フォンダの主演・監督作品で、アメリカン・ニューシネマの旗手らしく、従来の西部劇とは一線を画した内省的ともいえる異色の西部劇、ニューシネマとなっている。
最大の特長はリリカルな映像美で、オーバーラップやスローモーション、ストップモーションを多用し、西部の雄大で悠久の自然をゆったりとした演出で描き、映像詩ともいえるものに仕上げている。
物語は6年間放浪を共にしたコリングス(ピーター・フォンダ)とハリス(ウォーレン・オーツ)が、若いダン(ロバート・プラト)とともに西海岸を目指しながら寂れた町に立ち寄るところから始まる。ダンが町を支配するマクベイ(セヴァーン・ダーデン)の妻を襲ったという理由で殺されるが、それがダンの馬を手に入れるための罠だと察した二人はマクベイに重傷を負わせ、ダンの馬を取り返して町を出る。
西海岸行きに乗り気ではなかったコリングスは妻ハンナ(ヴァーナ・ブルーム)のいる家に帰ることに決め、ハリスも付いて行く。
ハンナは追い返そうとするが、コリングスは使用人として置いてもらうことにする。一方、町の噂でハンナがかつて使用人と寝ていたことを知る。これが原題の由来。
二人の仲を元通りにするために自分が邪魔だと感じたハリスは西海岸へと旅立つが、途中マクベイに捕まり、コリングスが呼び出される。反対するハンナよりハリスとの友情を選んだコリングスは救出に向かい、敢えなく死亡。遺体を馬に乗せてやってくるハリスを見て、ハンナが泣き崩れるシーンで終わる。
夢を追い求めて果たせなかった男たちと、それを見守るしかない女の悲話で、等身大の人間を描く、ヒーローなき西部劇となっている。 (評価:2.5)

課外教授
日本公開:1971年9月11日
監督:ロジェ・ヴァディム 製作:ジーン・ロッデンベリー 脚本:ジーン・ロッデンベリー 撮影:チャールズ・ロッシャー・Jr 音楽:ラロ・シフリン
原題"Pretty Maids All in a Row"で、可愛いメイドが全員列を成しての意。フランシス・ポリーニの同名小説が原作。
ハイスクールが舞台で、ガールフレンドはいないがすぐに勃起してしまうのが悩みのポンス君(ジョン・デイヴィッド・カーソン)が主人公。
転任女教師スミス先生(アンジー・ディッキンソン)のお尻に刺激されて早速トイレに駆け込むと、そこで女生徒の他殺死体発見! さてミステリーの始まりかと思いきや、アメフトコーチで副校長のタイガー(ロック・ハドソン)は心理学が専門で、女生徒のセックス・カウンセリングを実践中。
おまけに共学校なのにミニスカートの女生徒ばかりが目立って、捜査にやってきた警部(テリー・サヴァラス)はドラマ展開から追い出されて、ロジェ・ヴァディムのミステリーはどこに向かうのかいきなり迷走してしまう。
ポンス君はタイガー先生のカウンセリングを受けて、邦題通りにスミス先生の自宅でホームワークをすることになり、勃起症候群を解決!
一方、妻子持ちのタイガー先生は原題通りに片っ端から女生徒を食い物にした結果、結婚を迫られて次々に殺すことになり、最後は追い詰められて自殺。
と思いきや、それは偽装でメキシコにとんずら。女生徒たちの課外授業の後釜に悩み解決のポンス君が収まり、どういうわけかタイガー先生の妻も内緒でメキシコに飛び、警部がメキシコに追いかけるという、能天気なエンディングとなる。
ロジェ・ヴァディムのバカバカしくもお気楽に楽しめる、お色気ミステリーコメディ。
警部役のテリー・サヴァラスは、1973年から始まるテレビドラマ『刑事コジャック』の主役に抜擢されている。 (評価:2.5)

恋
日本公開:1972年2月11日
監督:ジョセフ・ロージー 製作:ジョン・ヘイマン 脚本:ハロルド・ピンター 撮影:ジェリー・フィッシャー 音楽:ミシェル・ルグラン
カンヌ映画祭グランプリ
原題"The Go-Between"で、仲介者の意。L・P・ハートレイの同名小説が原作。
夏休みを学校の友達のカントリーハウスで過ごすことになった少年が、友達の姉と小作人の恋を取り持つことになった苦い思い出を数十年後に回想するという物語。
身分違いの許されぬ恋が悲劇を生むという通俗的なロマンスを少年の視点で描くが、イングランド・ノーフォークの美しい田園風景と、ミシェル・ルグランの甘く不安を誘う調べが、不思議と心地よいセンチメンタルな気分にさせる。カンヌ国際映画祭グランプリ受賞。
時は1900年。母子家庭のレオ(マイケル・レッドグレイヴ)は領主の息子マーカス(リチャード・ギブソン)のカントリーハウスで夏休みを過ごすことになり、優しくて親切な姉のマリアン(ジュリー・クリスティ)に淡い恋心を抱く。しかしマリアンには恋人テッド(アラン・ベイツ)がいてレオは失恋に悲しむが、テッドが小作人であるために二人は仲を隠していて、頼まれてレオが恋文や伝言を運ぶマーキュリー(ギリシャ神話の伝令使ヘルメス、レオは水星と勘違いする)となる。
最後はそれがマーカスの母モーズレー夫人(マーガレット・レイトン)にバレてしまい、テッドは自殺、マリアンは子爵トリミンガム(エドワード・フォックス)と結婚。しかし、すでにマリアンはテッドの子を身籠っていて、数十年後、この事件のために結婚を躊躇している孫のためにレオを呼び寄せる…というのが物語の構図。
これが数十年後にマリアンと再会したレオの回想だということが終盤までわからず、しかも二人とも年をとっているために、それずらもわかりにくいというのが最大の難点。
孫が結婚に躊躇しているというのも言葉だけで、具体的に語られないのも、私たちの恋は美しかったという雰囲気だけの薄いものにしている。
少年の子供っぽい特技が呪いで、不条理な大人たちに対して滅んでしまえと呪いをかけ、その通り不幸が訪れ、カントリーハウスも寂れてしまうが、この伏線も上手く活きてない。
少年の思春期の性の目覚めと懐かしくも苦い思い出を描くが、これまたノスタルジックな雰囲気だけに終わっている。 (評価:2.5)

恐怖のメロディ
日本公開:1972年4月22日
監督:クリント・イーストウッド 製作:ロバート・デイリー 脚本:ディーン・リーズナー、ジョー・ヘイムズ 撮影:ブルース・サーティース 音楽:ディー・バートン
原題"Play Misty for Me"で、私のためにミスティをかけての意。
「ミスティ」はエロール・ガーナー作曲のバラードで、劇中、主人公デイブ(クリント・イーストウッド)がDJをしているラジオ番組に、イブリン(ジェシカ・ウォルター)が執拗にリクエストする。
カリフォルニアのモントレーが舞台。プロローグは美しい海岸線に建つデイブの恋人トビー(ドナ・ミルズ)の家の空撮から始まるが、エピローグも同じ場所の空撮で終わる。
デイブがイブリンにストーカーされる話で、イブリンの狂気が『羊たちの沈黙』(1988)のレクター教授よりも怖いというサイコ・ホラー。並のホラー映画の異形よりもイブリンの精神の方が遥かに怖く、イブリンが登場しただけで鳥肌が立つ。
主人公を演じるイーストウッドは演技にかけては大根で、恋人のドナ・ミルズも可愛いだけなので、レクター教授を演じるジェシカ・ウォルターのイッチャッタ演技が際立つ。
モテモテの遊び人デイブがイブリンと1回寝たのがきっかけでストーカーされまくり、ステップアップの仕事もフイに。家は荒らされ、家政婦はケガを負わされ、恋人まで巻き込んでしまうという、ホントに女は怖いという軽挙妄動を懲らしめる話。
劇中鍵となる「アナベル・リー」はエドガー・アラン・ポーの詩の中に登場する娘の名。愛し合った末に周囲の妨害により死んでしまうが、墓は海のほとりにあるというのが、本作のラストシーンを暗示している。 (評価:2.5)

製作国:イギリス
日本公開:1972年7月26日
監督:ジョン・ハフ 製作:ハリー・ファイン、マイケル・スタイル 脚本:チューダー・ゲイツ 撮影:ディック・ブッシュ 音楽:フィリップ・マーテル
プレイメイト双子姉妹の血も滴る豊満な胸
原題"Twins of Evil"で、邪悪の双子の意。
ハマー・フィルムの製作で、カルンシュタイン伯爵城下に住む叔父の村にやってきた双子の美人姉妹が主人公。
国王に守られた伯爵は女を買い、黒魔術にのめり込んで邪悪の限りを尽くし、ついには先祖の吸血鬼カーミラを召喚して自ら吸血鬼(undead)となることからもわかるが、シェリダン・レ・ファニュの『カーミラ』が基になっている。
不死者は鏡に映らない、十字架が苦手、退治方法は心臓に杭を打ち込むか首を撥ねるかで、焼いても魂は消滅せず新たな肉体に宿るという設定になっているが、新たな肉体に宿るという設定は活かされていない。
双子の叔父は魔女狩り集団のリーダーで、村で殺人が起きるたびに美人娘が邪悪の根源と火刑にして、とりわけ伯爵を目の敵にしているが、国王の庇護を怖れて手出しできずにいる。
そこで美人双子姉妹マリア、フリーダの登場となり、奢侈な伯爵に邪心を持つフリーダが城に出かけて吸血鬼にされ、自警団に捕まって裁きを受けるが、投獄中に伯爵がマリアと入れ替えてフリーダを城に連れ帰るというところで、双子設定が活かされる。
村の青年がマリアの窮地を救い、フリーダは首を撥ねられ、伯爵は胸に槍を打ち込まれてメデタシメデタシとなるが、伯爵が朽ちていくシーンが映像的な見どころ。
バンパイアハンターのリーダーである叔父をピーター・カッシングが演じるが、伯爵退治の見せ場は青年に奪われている。
伯爵城下の村娘たちは美人ぞろいで、伯爵の邪心も納得できてしまうが、双子姉妹を演じるのはマリー・コリンソンとマドレーヌ・コリンソンで、前年にプレイボーイ誌初の双子プレイメイトに選ばれていて、本作でも豊満な胸を披露している。 (評価:2.5)

日本公開:1972年7月26日
監督:ジョン・ハフ 製作:ハリー・ファイン、マイケル・スタイル 脚本:チューダー・ゲイツ 撮影:ディック・ブッシュ 音楽:フィリップ・マーテル
原題"Twins of Evil"で、邪悪の双子の意。
ハマー・フィルムの製作で、カルンシュタイン伯爵城下に住む叔父の村にやってきた双子の美人姉妹が主人公。
国王に守られた伯爵は女を買い、黒魔術にのめり込んで邪悪の限りを尽くし、ついには先祖の吸血鬼カーミラを召喚して自ら吸血鬼(undead)となることからもわかるが、シェリダン・レ・ファニュの『カーミラ』が基になっている。
不死者は鏡に映らない、十字架が苦手、退治方法は心臓に杭を打ち込むか首を撥ねるかで、焼いても魂は消滅せず新たな肉体に宿るという設定になっているが、新たな肉体に宿るという設定は活かされていない。
双子の叔父は魔女狩り集団のリーダーで、村で殺人が起きるたびに美人娘が邪悪の根源と火刑にして、とりわけ伯爵を目の敵にしているが、国王の庇護を怖れて手出しできずにいる。
そこで美人双子姉妹マリア、フリーダの登場となり、奢侈な伯爵に邪心を持つフリーダが城に出かけて吸血鬼にされ、自警団に捕まって裁きを受けるが、投獄中に伯爵がマリアと入れ替えてフリーダを城に連れ帰るというところで、双子設定が活かされる。
村の青年がマリアの窮地を救い、フリーダは首を撥ねられ、伯爵は胸に槍を打ち込まれてメデタシメデタシとなるが、伯爵が朽ちていくシーンが映像的な見どころ。
バンパイアハンターのリーダーである叔父をピーター・カッシングが演じるが、伯爵退治の見せ場は青年に奪われている。
伯爵城下の村娘たちは美人ぞろいで、伯爵の邪心も納得できてしまうが、双子姉妹を演じるのはマリー・コリンソンとマドレーヌ・コリンソンで、前年にプレイボーイ誌初の双子プレイメイトに選ばれていて、本作でも豊満な胸を披露している。 (評価:2.5)

パリは霧にぬれて
日本公開:1971年12月11日
監督:ルネ・クレマン 脚本:ルネ・クレマン、ダニエル・ブーランジェ 撮影:アンドレア・ウィンディング 音楽:ジルベール・ベコー
原題"La Maison sous les Arbres"で、木々の下の家の意。アーサー・カバノーの小説が原作。
アメリカからパリに移り住んだ家族4人が不可解な事件に巻き込まれるというサスペンスドラマで、子供を誘拐される情緒不安定な母親をフェイ・ダナウェイが演じる甘ったるいフランス映画というのが最大の見どころだが、本格的なサスペンスを期待するかフランスのエスプリを選ぶかが評価の分かれ目。
夫のフィリップ(フランク・ランジェラ)は電子工学技術者で、ヤバい仕事をしていたことからアメリカを逃れ、パリで専門書の執筆をしている。しかし、組織はそれを許さず、ついに子供2人を誘拐して復職を強要するという物語。
妻のジル(フェイ・ダナウェイ)は思いつきで行動するという情緒不安定で、健忘症もあって精神科通い。ジルの血を引く幼い息子も糸の切れた凧のような性格で、それが原因で行方不明になってしまう。
そんな糸の切れた凧を放任するジルも、能天気というよりは物を考えない欠陥人間で、組織に関係する隣人がメモを見ながらかけた鍵となる電話番号を思い出せないと刑事に言うが、隣人の家にメモがあることに気づかない。
そもそも夫の出版パーティのある日に、子連れで指人形劇を見に行くのも無計画で、だから子供を誘拐されてしまう。ただ、そのために夫が妻の来ないことから事件に気づくという良く出来たシナリオ。
監視者を殺したのに子供2人は逃げ出さないとか、随所にサスペンスよりもフランスのエスプリが利いている。
ジルベール・ベコーのシャンソンな音楽を含めて、どちらかといえば夫婦仲の上手くいかなくなった男女の愛の復活のドラマだが、家族それぞれの人物描写がイマイチで、雰囲気だけでみる作品。
サスペンスとしては組織が何なのか、最後まで不明。 (評価:2)

哀しみの街かど
日本公開:1971年11月20日
監督:ジェリー・シャッツバーグ 製作:ドミニク・ダン 脚本:ジョーン・ディディオン、ジョン・グレゴリー・ダン 撮影:アダム・ホレンダー
原題"The Panic in Needle Park"で、ニードルパークのパニックの意。ジェームズ・ミルズの同名小説が原作。
ニードルパークは1960~70年代、マンハッタンのアッパー・ウエスト・サイドの一角の俗称で、麻薬常習者とディーラーが集まっていた場所。Needleは注射針のこと。Panicは劇中でヘロインの供給が止まってしまうことを指す。
麻薬で身を滅ぼす若者を描く啓発映画としては百点満点の出来だが、制作者はもちろんそんなことは考えてなく、1970年代という若者たちが確かな未来を描けずに麻薬に逃避する時代と退廃を描き、当時の若者たちの心の傷を舐めて精神を慰撫する。
そうした点で全編に渡って70年代の空気が充満していて、一目見てアメリカン・ニューシネマだとわかるのだが、当時の空気を吸った者には懐かしさと共に重苦しさとある種の蹉跌を感じる。
主人公は田舎から出てきた画家の卵の女の子で、ソーホーで男と暮し堕胎。そこに麻薬と窃盗の海図なき青春を送る青年が現れ、その優しさに魅かれて恋人となる。女の子はやがてヘロインに手を出し、麻薬を手に入れるために売春するが、彼女に同情的な刑事は麻薬の元締めを挙げるために逮捕と引き換えに恋人を売らせる。
逮捕され収監された恋人は出所に迎えにきた娘を赦して歩き出すが、二人に希望のないままに終わる。
本作で描かれるのは夢も希望もない人生だが、夢と希望をなくしたのは誰のせいでもなくこの二人自身という自業自得の青春で、彼らの惨めさの背景にベトナム戦争もなければ学園紛争も貧困も人種差別もない。そんな二人に共感するとすれば、せいぜいが潜在的なドロップアウト願望でしかない。 (評価:2)

製作国:フランス
日本公開:1978年2月25日
監督:ロベール・ブレッソン 脚本:ロベール・ブレッソン 撮影:ピエール・ロム 音楽:ミシェル・マーニュ、グループ・バトゥーキ、クリストファー・ヘイワード、ルイ・ギター、F・R・ダビド
キネマ旬報:8位
延々と退屈な時間が流れるがヌードシーンになると目が覚める
原題"Quatre nuits d'un rêveur"で、夢想家の四夜の意。ドストエフスキーの短編小説"Beliya nochi"(白夜)の翻案。
独りぼっちの画家(ギョーム・デ・フォレ)が、身投げしようとしている少女(イザベル・ベンガルテン)を助ける。彼女は一年後に再会を約した恋人が現れず、画家が仲介して連絡を取り毎晩二人で待つことになるが、やはり恋人は現れず、次第に少女が好きになってしまった画家は愛を告白。四日目の晩、少女は恋人を忘れて画家を恋人にするが、偶然元恋人と遭遇。少女は画家を捨てて元恋人と去ってしまうという、トンビに油揚げを攫われるという、悲しい話。
物語は淡々と進むが、芝居的演技を嫌う演出が悪いのか、内面的演技のできない俳優が下手なのか、延々と退屈な時間が流れ、ラストはドストエフスキー文学というよりは、皮肉で教訓的なフランス小噺になっているのが、さすがに色恋沙汰が好きなフランス映画。
ロシア的な内面的で陰鬱な人間ドラマには程遠く、おフランス的な軽薄な恋愛譚になっているため、ドラマ性が稀薄で単調、睡魔がたびたび襲う。
唯一の見どころは少女役のイザベル・ベンガルテンで、ヌードシーンになると目が覚める。 (評価:2)

日本公開:1978年2月25日
監督:ロベール・ブレッソン 脚本:ロベール・ブレッソン 撮影:ピエール・ロム 音楽:ミシェル・マーニュ、グループ・バトゥーキ、クリストファー・ヘイワード、ルイ・ギター、F・R・ダビド
キネマ旬報:8位
原題"Quatre nuits d'un rêveur"で、夢想家の四夜の意。ドストエフスキーの短編小説"Beliya nochi"(白夜)の翻案。
独りぼっちの画家(ギョーム・デ・フォレ)が、身投げしようとしている少女(イザベル・ベンガルテン)を助ける。彼女は一年後に再会を約した恋人が現れず、画家が仲介して連絡を取り毎晩二人で待つことになるが、やはり恋人は現れず、次第に少女が好きになってしまった画家は愛を告白。四日目の晩、少女は恋人を忘れて画家を恋人にするが、偶然元恋人と遭遇。少女は画家を捨てて元恋人と去ってしまうという、トンビに油揚げを攫われるという、悲しい話。
物語は淡々と進むが、芝居的演技を嫌う演出が悪いのか、内面的演技のできない俳優が下手なのか、延々と退屈な時間が流れ、ラストはドストエフスキー文学というよりは、皮肉で教訓的なフランス小噺になっているのが、さすがに色恋沙汰が好きなフランス映画。
ロシア的な内面的で陰鬱な人間ドラマには程遠く、おフランス的な軽薄な恋愛譚になっているため、ドラマ性が稀薄で単調、睡魔がたびたび襲う。
唯一の見どころは少女役のイザベル・ベンガルテンで、ヌードシーンになると目が覚める。 (評価:2)

好奇心
日本公開:1972年4月15日
監督:ルイ・マル 製作:ヴァンサン・マル、クロード・ネジャール 脚本:ルイ・マル、クロード・ネジャール 美術:ジャン・ジャック・カジオ、フィリップ・ターラー 撮影:リカルド・アロノヴィッチ 音楽:チャーリー・パーカー
原題"Le Souffle au Coeur"で、心の呟やきの意。
15歳の少年が蛹から羽化する話。単なる思春期の成長物語と違うのは、少年がマザコンで、母親も過保護。おまけにセクシーな母は大人の男だけでなく、若い青年や同性の少女でさえ振り返るほどに若々しくセクシーで、少年と一緒に歩いていても恋人同士のように見えること。
朝起きれば抱擁、学校から帰れば抱擁というまるで幼児並みに乳離れできてなく、女遊びをしている兄2人とは大違いの母子関係。
兄2人に売春クラブに連れて行かれるが、筆おろしも中途半端に終わってしまい、なかなか大人になれない。
ルイ・マルにとっては女との初体験が、少年か大人かを分ける基準らしく、思春期から大人への脱皮の指標となっている。
そう言われれば、日本でも女を知ること即ち大人になることといった観念が昔からあって、売防法以前は旧制高校生が遊郭に行って大人になるといった描写が映画にもよくあった。
そのフランス版と考えれば納得もいくが、本作ではその初体験をホテル滞在中に愛人と失恋した母親で済ませてしまうというのが何とも言えず、その思い出はいつまでも胸にしまっておくのよ、と母に言われるというマザコン少年の甘美な体験となっている。
これによって少年は乳離れし、正常な母子の関係におそらくなるのだが、その直後、ホテルで知り合った好きでもない女の子と一夜を明かすという、立派な大人への羽化ぶりを示す…
と講評するのもバカバカしい作品なのだが、母を演じるレア・マッサリ38歳が少年の気持ちもわかるくらいに艶っぽいのが見どころか。 (評価:2)

007 ダイヤモンドは永遠に
日本公開:1971年12月25日
監督:ガイ・ハミルトン 製作:ハリー・サルツマン、アルバート・R・ブロッコリ 脚本:トム・マンキウィッツ、リチャード・メイボーム 撮影:テッド・ムーア 音楽:ジョン・バリー
原題は"Diamonds Are Forever"で、邦題の意。シリーズ第7作。イアン・フレミングの同名小説が原作。
ショーン・コネリーがボンド役に復帰するのもの、これが「ネバーセイ・ネバーアゲイン」(1983)を除く、シリーズ最後の出演作となった。
南アフリカからのダイヤモンド密輸の捜査を命じられたボンドがアムステルダムからネバダに飛ぶ。背後にはスペクターのブロフェルドがいて、なんとダイヤモンドは人工衛星に乗せられて、宇宙からレーザー光で米ソ中のミサイルや軍事施設を破壊する。これを遠隔操作するテープを奪取して、スペクターの企みを阻止するというのが物語の大筋。
ストーリーはともかく、見どころはアムステルダム運河観光もあるが、半世紀近く前のラスベガス。当時のカジノやサーカスなどのショーが垣間見れる。月面車やバギーでの荒野のチェイスも、月面着陸が話題となった当時を思い出させる。
ダイヤモンド密輸屋となるボンドガールは、ジル・セント・ジョン。冒頭のシーンはジョージ・レーゼンビーの前作ではなく、前々作のショーン・コネリーの『007は二度死ぬ』の舞台・日本というのも楽屋落ちとしては面白いが、全体の後半はやや冗長で飽きる。
シャーリー・バッシーの主題歌は『ゴールドフィンガー』に続く2度目。 (評価:2)

新・猿の惑星
日本公開:1971年7月31日
監督:ドン・テイラー 製作:アーサー・P・ジェイコブスル 脚本:ポール・デーン 撮影:ジョセフ・バイロック 音楽:ジェリー・ゴールドスミス
原題は"Escape from the Planet of the Apes"(猿の惑星からの脱出)。『猿の惑星』シリーズ3作目。
前作で2000年後の地球が滅び、ジーラ(キム・ハンター)たち3匹が現代の地球にやってくるという、逆ヴァージョン。
ここまでくると第1作のパロディで、言葉を話す猿がいたらどうなるかというコメディでしかなく、当初のSF的興趣は完全に薄れる。これをSFだと思ってみると大いに失望するので、単にシニカルなアメリカン・コメディだと思ってみた方が良い。
湖底に沈んだ宇宙船を調べていたら、核爆発とともにタイムスリップしてしまったという設定で、都合よくテイラー出発後の地球にくる。アメリカ大統領以下の政治家、科学者たちがジーラたちを調査するが、鎖に繋がれて動物園の檻に入れられるという虐待ぶり。
世論で高級ホテルに移されるも、果たして動物はホテルに宿泊できるのか? 検疫はしないのか? とか余計なことを考えてしまうが、そこはコメディだからと納得するしかない。
自白剤を注射して、猿に滅ぼされる人類の未来を知った悪い科学者は、妊娠して子供を産んだ猿の夫婦の抹殺を図るが、サーカスの一団に匿われたジーラはチンパンジーの母子を見て・・・と、この段階でラストが容易に想像がつく。
こうして現代から2000年後の未来までの物語となる続編2作へと続くのだが、もともと人類による地球環境の破壊と進化論の物語だったのが、なんで未来に原因があるというタイム・パラックスの話になってしまったのか? 流れが『ターミネーター』によく似ているが、もちろん、こちらが先行作品。
第1作からの変質を見ると、ずいぶんと遠くに来てしまった感があって、第1作のファンには禁断の地ならぬ、禁断の『猿の惑星』。 (評価:2)

ブラック・ライダー
no image
製作国:アメリカ日本公開:1972年6月28日
監督:シドニー・ポワチエ 製作:ジョエル・グリックマン 脚本:アーネスト・キノイ 撮影:アレックス・フィリップス・Jr 音楽:ベニー・カーター
原題"Buck and the Preacher"で、バックと牧師の意。バックは主人公の名。
南北戦争終了後の奴隷解放によって、黒人たちが農地を求めて西進。バック(シドニー・ポワチエ)は幌馬車隊の道案内役で、通過のための先住民との交渉もする。
一方、人手不足に陥った南部の農場主は、幌馬車隊に嫌がらせをして黒人を元の場所に引き返させようとするのが争いのモトで、邪魔なバックを排除しようとして双方が対立する。そこに絡むのが黒人牧師のラザフォード(ハリー・ベラフォンテ)で、始めは賞金欲しさにバックに近づくが、白人たちの残虐行為にバックと手を組む。
それで勧善懲悪なら良いのだが、二人して銀行強盗をする段になると、いくら被差別者の復讐の論理とはいえ、倫理的には良しとは言えないところがあって、あまり気持ちの良いものではない。
いわゆる黒人観客向けに作られたブラックスプロイテーションともいえ、白人の悪党を黒人のガンマン二人組がスイープしていくという、黒人から見ればこの上なく爽快な西部劇で、悪乗りして銀行強盗しようが気にしないという展開。
最後はインディアンが味方してくれるという、同じマイノリティだからという都合の良さがどうにも気分が悪く、先住民からすれば白人も黒人も海を渡ってやってきた侵略者という発想がないのが、肌の黒い白人ポワチエの限界を示している。 (評価:2)

アンドロメダ…
日本公開:1971年8月28日
監督:ロバート・ワイズ 製作:ロバート・ワイズ 脚本:ネルソン・ギディング 撮影:リチャード・クライン 音楽:ギル・メレ
原題"The Andromeda Strain"で、アンドロメダ菌株の意。マイケル・クライトンの同名SF小説が原作。
ニューメキシコ州の村に落下した軍用衛星から未知の微生物が住民に感染、村が全滅する。生き残った赤ん坊と老人を回収、アンドロメダ菌株と名付けられた微生物の謎を緊急招集された科学者たちに分析させるが、感染が研究所内に広がり核自爆装置が作動。
血液のph(ペーハー)が感染の治療に役立つことに気づいたホール博士(ジェームズ・オルソン)は、ストーン博士(アーサー・ヒル)の援護を受けながら、自爆装置を解除させる鍵を持って残り5分のタイムレースに挑むという物語。
解除はもちろん成功するが、村からの感染拡大を防ぐための核爆発によって発生したアンドロメダ菌株の雲を海に誘導して雨となって溶け込ませれば、弱アルカリなので消滅するという楽観的な言葉で締めくくられる。
細菌汚染を防ぐために核爆弾を使うという発想や、アンドロメダへの対処法が酸性・アルカリ性といったオチが本作のSF度を示しているが、冒頭死人だらけの村で、硬直死体が物理法則に反して立っているという安易な演出もSFとしての興趣を削ぐ。
アンドロメダによって血液が粉末になる理由も説明されないし、やたらSF的な専門用語らしきものを連発するだけの台詞もわけが分からなく、研究室中心のテンポの悪さで何度も睡魔が襲う。
本格的なSFを目指すか、SFそっちのけのアクション映画のどっちかにした方が良かったのでは、というのが実感。
微生物が何でアンドロメダと命名されたのかというのもよくわからない。 (評価:2)

わたしは目撃者
日本公開:1972年10月28日
監督:ダリオ・アルジェント 製作:サルヴァトーレ・アルジェント 脚本:ダリオ・アルジェント 撮影:エンリコ・メンチェール 音楽:エンニオ・モリコーネ
原題"Il gatto a nove code"で、九尾の猫の意。
アルジェントの初監督『歓びの毒牙』に続く駄作で、ストーリーが無茶苦茶なサスペンス。
盲人と新聞記者が探偵ごっこをするが、新聞記者はともかく、盲人が趣味以外に犯人探しに加わる必然性が全くなく、絵面の面白さを狙っただけ。とりわけ冒頭は同居する孤児の女の子が目の代わりをするが、この二人が歩くのが絵になっていて、二人の活躍を期待するが、少女は事件が本格化すると危険だと預けられて退場してしまう。
あとは盲人と新聞記者が事件を追う展開で、遺伝子研究所の不法侵入事件と研究所の教授の死を発端に、事件に関係した者が殺されていく。
結末を書けば、ある男が犯人だが、この男は冒頭に1回登場するだけで、最後に犯人は○○だったのか!と言われても、はて誰だっけ?という有り様。しかも途中ロケットに隠された住所の書かれた紙片も、ラストの謎解きには生きてこず、ただ犯人がそれを取り戻そうとするだけの道具。誰の住所なのかもわからないまま。盲人が仕込み杖を持っている理由も、犯人が何のために事務所荒らしと殺人を犯したのかも説明されないまま。
唯一、見どころを見出せば、ラスト以外犯人が主観視点の瞳だけでしか登場しないことで、これと座頭市のアイディアだけで作品が作られている。
美少女も幼すぎて、ラストに誘拐されて縛られるシーン以外に見せ場はない。 (評価:1.5)

日本公開:1977年1月22日
監督:マイケル・カコヤニス 製作:マイケル・カコヤニス、アニス・ノーラ 脚本:マイケル・カコヤニス 撮影:アルフィオ・コンチーニ 音楽:ミキス・テオドラキス
キネマ旬報:8位
原題"The Trojan Women"。エウリピデスの戯曲『トロイアの女』が原作。