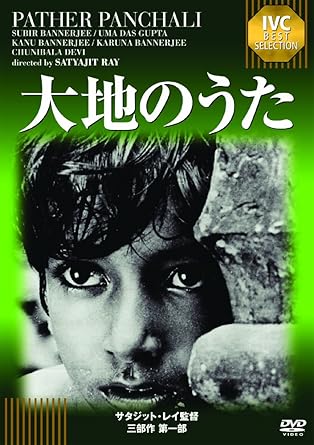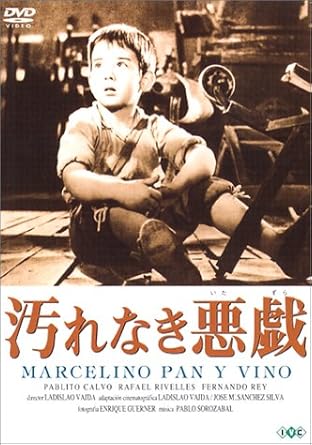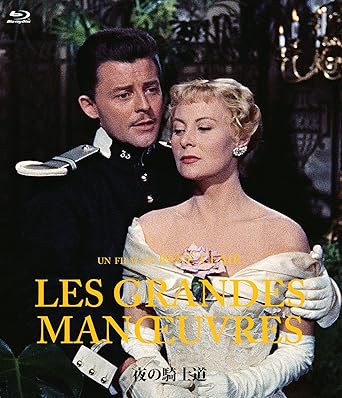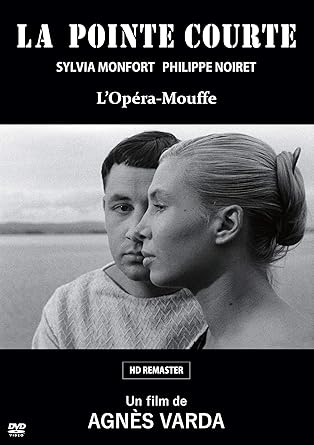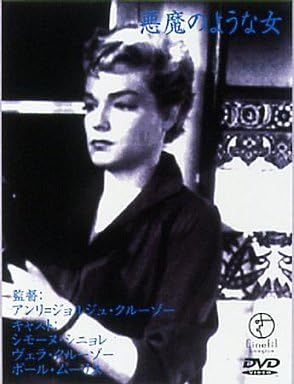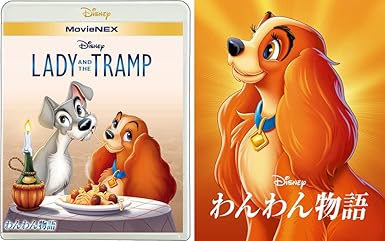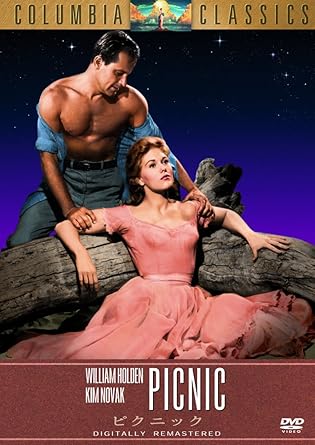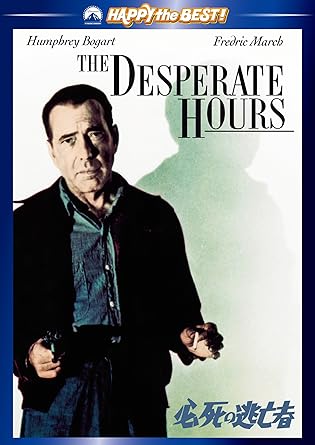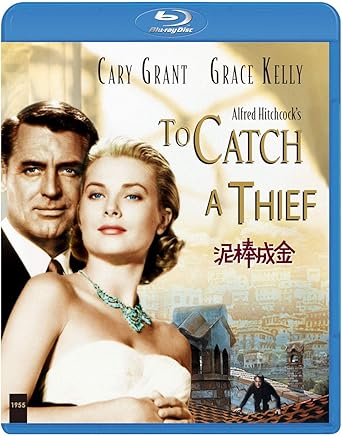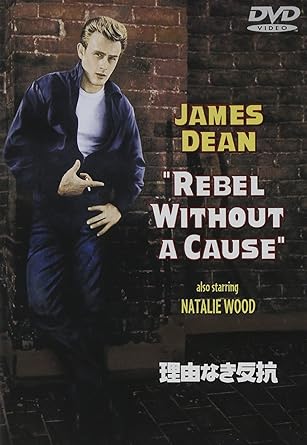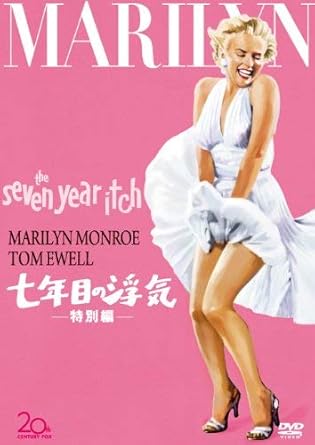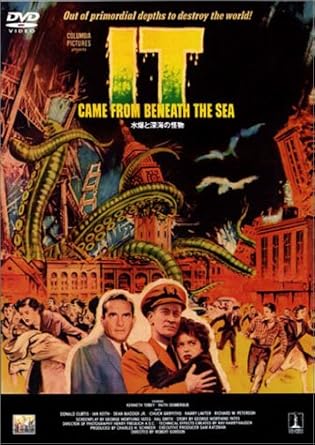外国映画レビュー──1955年
製作国:イギリス
日本公開:1955年10月4日
監督:デヴィッド・リーン 製作:イルヤ・ロパート 脚本:H・E・ベイツ、デヴィッド・リーン 撮影:ジャック・ヒルデヤード 音楽:アレッサンドロ・チコニーニ
キネマ旬報:4位
ゴールデングローブ作品賞
イタリアでは食事を食べるが、パリではソースを食べる
原題は"Summertime"で、中年女のヴェネツィアでのひと夏の恋物語。原作はアーサー・ローレンツの戯曲『カッコウ鳥の頃』(The Time of the Cuckoo)。
38歳の独身アメリカ女(キャサリン・ヘプバーン)がヴェネツィアに初めての海外旅行をする。8ミリカメラを回して美しい風景を撮りまくる観光気分なのだが、ホテルで同宿する人たちはカップルばかりで、一人旅の寂しさに次第に気が沈んでいく。宿の女主人はそんな彼女をお見通しで、地元の人と交流しなければ恋は生まれないとアドバイスするが、プライドが高く弱みを見せたくない女は、観光客相手に小銭を稼ぐ少年と見物を続ける。
そんな彼女を見かけた骨董店主(ロッサノ・ブラッツィ)がナンパ。始めは頑なに拒む彼女も、旅でのfall-in-love願望が勝って急激に恋に落ちる。ところが独身だと思っていた男に妻子がいることを知って落胆。しかし相手は開き直って、結婚がなんだ、好きなら愛し合えばいいと、イタリア男のラテン気質で攻める。
アングロサクソンの女はピューリタン精神に反すると拒むが、旅の開放気分からか男に傾倒。しかし思い直してヴェネツィアを去る。
40年後の『マディソン郡の橋』(1995、ロバート・ジェームズ・ウォラー原作)を思い出させる中年男女のアバンチュール映画だが、ヘプバーン48歳で65歳のクリント・イーストウッドの老いらくの恋には敵わないが、立派に壮年の恋に見える。マディソン郡では旅人は男でカメラマン。本作と男女が入れ替わっている。
大人のアバンチュールの見どころは2点あって、一つは美人だが恋に臆病で独身を通してきた女が外国という非日常の中で自らを抑圧していたものを解放し、おそらく生涯で最初の恋を経験すること。しかし、それを非日常に咲いた仇花だと見通して、現実の前に枯らせるのではなく、思い出として永遠に咲かせておくべきだということに気づくこと。まさしく、大人の恋。
もう一つの見どころは男が彼女に恋したことは間違いないが、それが妻と別れて結婚するつもりだったのか、ラテン男の本能として、妻と愛人は分けて考えていたのか最後まで不明で、最後に渡せなかったプレゼントが何だったのかという謎を含めて、ヴェネツィアの風景と一体化した、好きならそれでいいじゃないのという、ふやけた気分に浸れること。男ならラテン気質の真髄を垣間見れるかもしれない。これも、大人の恋。
旅には始まりがあって必ず終わりがある。その永遠の定理を本作は美しいヴェネツィアとともに描く。キャサリン・ヘプバーンが上手い。 ホテルの女主人の台詞が使える。"In Italy you sit down to eat and you eat a meal. In Paris you sit down to eat and what do you eat? A sauce."(イタリアでは食事を食べるが、パリではソースを食べる) (評価:4)

日本公開:1955年10月4日
監督:デヴィッド・リーン 製作:イルヤ・ロパート 脚本:H・E・ベイツ、デヴィッド・リーン 撮影:ジャック・ヒルデヤード 音楽:アレッサンドロ・チコニーニ
キネマ旬報:4位
ゴールデングローブ作品賞
原題は"Summertime"で、中年女のヴェネツィアでのひと夏の恋物語。原作はアーサー・ローレンツの戯曲『カッコウ鳥の頃』(The Time of the Cuckoo)。
38歳の独身アメリカ女(キャサリン・ヘプバーン)がヴェネツィアに初めての海外旅行をする。8ミリカメラを回して美しい風景を撮りまくる観光気分なのだが、ホテルで同宿する人たちはカップルばかりで、一人旅の寂しさに次第に気が沈んでいく。宿の女主人はそんな彼女をお見通しで、地元の人と交流しなければ恋は生まれないとアドバイスするが、プライドが高く弱みを見せたくない女は、観光客相手に小銭を稼ぐ少年と見物を続ける。
そんな彼女を見かけた骨董店主(ロッサノ・ブラッツィ)がナンパ。始めは頑なに拒む彼女も、旅でのfall-in-love願望が勝って急激に恋に落ちる。ところが独身だと思っていた男に妻子がいることを知って落胆。しかし相手は開き直って、結婚がなんだ、好きなら愛し合えばいいと、イタリア男のラテン気質で攻める。
アングロサクソンの女はピューリタン精神に反すると拒むが、旅の開放気分からか男に傾倒。しかし思い直してヴェネツィアを去る。
40年後の『マディソン郡の橋』(1995、ロバート・ジェームズ・ウォラー原作)を思い出させる中年男女のアバンチュール映画だが、ヘプバーン48歳で65歳のクリント・イーストウッドの老いらくの恋には敵わないが、立派に壮年の恋に見える。マディソン郡では旅人は男でカメラマン。本作と男女が入れ替わっている。
大人のアバンチュールの見どころは2点あって、一つは美人だが恋に臆病で独身を通してきた女が外国という非日常の中で自らを抑圧していたものを解放し、おそらく生涯で最初の恋を経験すること。しかし、それを非日常に咲いた仇花だと見通して、現実の前に枯らせるのではなく、思い出として永遠に咲かせておくべきだということに気づくこと。まさしく、大人の恋。
もう一つの見どころは男が彼女に恋したことは間違いないが、それが妻と別れて結婚するつもりだったのか、ラテン男の本能として、妻と愛人は分けて考えていたのか最後まで不明で、最後に渡せなかったプレゼントが何だったのかという謎を含めて、ヴェネツィアの風景と一体化した、好きならそれでいいじゃないのという、ふやけた気分に浸れること。男ならラテン気質の真髄を垣間見れるかもしれない。これも、大人の恋。
旅には始まりがあって必ず終わりがある。その永遠の定理を本作は美しいヴェネツィアとともに描く。キャサリン・ヘプバーンが上手い。 ホテルの女主人の台詞が使える。"In Italy you sit down to eat and you eat a meal. In Paris you sit down to eat and what do you eat? A sauce."(イタリアでは食事を食べるが、パリではソースを食べる) (評価:4)

製作国:インド
日本公開:1966年10月11日
監督:サタジット・レイ 脚本:サタジット・レイ 撮影:スプラタ・ミットラ 音楽:ラヴィ・シャンカール
キネマ旬報:1位
20世紀初頭のインドの地方の生活や風俗が興味深い
原題"পথের পাঁচালী"で、ベンガル語で道の歌の意。ビブティブション・ボンドパッダエの同名の自伝的小説が原作。
舞台は西ベンガル州のバラクプール村、借金のために果樹園を売り払い、極貧の生活に陥った一家の物語。
ヒンドゥーの学問を修めた僧侶の父親(カヌ・バナールジ)は生活力に乏しく、詩作に打ち込んで仕事もままならない。本人はそれでよいと考えるインド哲学的な価値観の持ち主で、妻(コルナ・バナールジ)と娘・息子は朽ちかけた家で、日に二度の食事も食べられないでいる。
一家に老女の叔母が居候しているが、食べる物もなく、姪(ウマ・ダス・グプタ)が地主の果樹園から盗んできた果物をもらっている。そんな家族の日々を追うが、やがて叔母が老衰死し、嵐の日に風邪を引いた娘もそれが原因で死んでしまう。そして一家は村を捨て新天地を求めて旅立つ、というのがラスト。
本編の主人公は姉で、それを弟の目を通して描くが、この弟オプ(サビル・バナルジー)が原作者自身。
姉は、果物ばかりか地主の娘のネックレスも盗み、弟は姉の死後、引っ越しの準備中にそれを発見する。主題となるのはインド的な法で、姉は叔母への喜捨のために果物を得、同時に貧者である自分も地主から施しを受ける身であることを実践する。
僧であり学者でもある父は物欲を離れ、金よりも法に価値をおくが、象徴的なのは喜捨を求めて訪れる乞食僧に対し、母が施す事さえできないことで、近代へと移りゆくインドの思想的葛藤が描かれることになる。
そうしたテーマを離れても、この極貧一家の物語は面白く、20世紀初頭のインドの地方の生活や風俗が興味深い。 (評価:3.5)

日本公開:1966年10月11日
監督:サタジット・レイ 脚本:サタジット・レイ 撮影:スプラタ・ミットラ 音楽:ラヴィ・シャンカール
キネマ旬報:1位
原題"পথের পাঁচালী"で、ベンガル語で道の歌の意。ビブティブション・ボンドパッダエの同名の自伝的小説が原作。
舞台は西ベンガル州のバラクプール村、借金のために果樹園を売り払い、極貧の生活に陥った一家の物語。
ヒンドゥーの学問を修めた僧侶の父親(カヌ・バナールジ)は生活力に乏しく、詩作に打ち込んで仕事もままならない。本人はそれでよいと考えるインド哲学的な価値観の持ち主で、妻(コルナ・バナールジ)と娘・息子は朽ちかけた家で、日に二度の食事も食べられないでいる。
一家に老女の叔母が居候しているが、食べる物もなく、姪(ウマ・ダス・グプタ)が地主の果樹園から盗んできた果物をもらっている。そんな家族の日々を追うが、やがて叔母が老衰死し、嵐の日に風邪を引いた娘もそれが原因で死んでしまう。そして一家は村を捨て新天地を求めて旅立つ、というのがラスト。
本編の主人公は姉で、それを弟の目を通して描くが、この弟オプ(サビル・バナルジー)が原作者自身。
姉は、果物ばかりか地主の娘のネックレスも盗み、弟は姉の死後、引っ越しの準備中にそれを発見する。主題となるのはインド的な法で、姉は叔母への喜捨のために果物を得、同時に貧者である自分も地主から施しを受ける身であることを実践する。
僧であり学者でもある父は物欲を離れ、金よりも法に価値をおくが、象徴的なのは喜捨を求めて訪れる乞食僧に対し、母が施す事さえできないことで、近代へと移りゆくインドの思想的葛藤が描かれることになる。
そうしたテーマを離れても、この極貧一家の物語は面白く、20世紀初頭のインドの地方の生活や風俗が興味深い。 (評価:3.5)

製作国:アメリカ
日本公開:1955年12月15日
監督:デルバート・マン 製作:ハロルド・ヘクト 脚本:パディ・チャイエフスキー 撮影:ジョセフ・ラシェル 音楽:ロイ・ウェッブ
キネマ旬報:7位
アカデミー作品賞 カンヌ映画祭パルム・ドール
婚活、パラサイト、核家族と現代的テーマが目白押し
原題"Marty"で、主人公の名。1953年にNBCで放映されたテレビドラマの映画化。
34歳の独身男の婚活を描いた作品で、1950年代と時代こそ違え、意外と現代にも通じる作品。
容貌もイマイチなbutcher(精肉店員)は、父の死で大学進学を諦め、結婚していった弟妹と母の面倒を見るうちに結婚しそびれ、周囲からは結婚を勧められるものの女の子には相手にされず、惨めな気分を味わっている。
そこに息子夫婦とそりの合わない叔母を引き取る話が来て、心優しいbutcherは快諾するが、そうした生活にも嫌気がさして、友達とお見合いダンスパーティに出かける。
パートナーの見つからないbutcherは、同行者に置いてけぼりを喰らって泣いている女の子に同情し、ダンスに誘う。29歳のクララは老けて見える上に大卒の高校教師というイモ女だが、二人はすっかり意気投合。夜遅くまでお喋りした上にキスまで交わし、翌日のデートを約束する。
ところが息子の結婚を望んでいたはずの母は、妹同様、自分が放り出されることを心配して良い顔をせず、友達も遊びの付き合いを強要する。周囲の不同意に心優しいbutcherはデートを放り出そうとするが、意を決して彼女に電話をするところで物語は終わる。
結婚相手の見つからない男女、婚活パーティ、パラサイト、核家族と現代に通用するテーマが目白押しで、日本社会がむしろ当時のアメリカに近づいたのかもしれない。
醜男と醜女という設定の男女を演じるアーネスト・ボーグナインとベッツィ・ブレアは、年齢を除けばごく普通の容姿で若干違和感があるが、「あなたはいい人よ」と訳された台詞が、"You're a good butcher."なのが可笑しい。
劇中、マーティがクララに「母には僕が必要だと言ってきたが、本当はそうじゃない。お父さんを必要としているのは君なんだ。お父さんやお母さんとずっと一緒にいることはできるけれど、一生、君は親離れできないままだ」(I used to think about moving out, you know? And that's what I used to say. "My mother needs me." But when you really get down to it, that ain't it at all. Actually, you need your father. You know what I mean? You're living at home, and you got your father and mother there, and you can go on like that -- being a little girl all your life.)という台詞が本作の核心部分。
親の世話を言い訳にマーティ自身が親離れできないことを自覚し、新しい人生に踏み出そうとする。
マーティはイタリア系で、誰よりもママンが大事、仲間が大切という背景もあるが、マーティの決意の後に予想されるママンや仲間との軋轢は描かれない。本来なら、そこをマーティがどう乗り越えていくかが本題だが、ニューシネマ以前のヒューマンドラマのため、善意を信じるハッピーエンド。
その後が心配ながらも、往年のハリウッド映画の心地よい余韻がいい。カンヌ映画祭パルム・ドール受賞。 (評価:3)

日本公開:1955年12月15日
監督:デルバート・マン 製作:ハロルド・ヘクト 脚本:パディ・チャイエフスキー 撮影:ジョセフ・ラシェル 音楽:ロイ・ウェッブ
キネマ旬報:7位
アカデミー作品賞 カンヌ映画祭パルム・ドール
原題"Marty"で、主人公の名。1953年にNBCで放映されたテレビドラマの映画化。
34歳の独身男の婚活を描いた作品で、1950年代と時代こそ違え、意外と現代にも通じる作品。
容貌もイマイチなbutcher(精肉店員)は、父の死で大学進学を諦め、結婚していった弟妹と母の面倒を見るうちに結婚しそびれ、周囲からは結婚を勧められるものの女の子には相手にされず、惨めな気分を味わっている。
そこに息子夫婦とそりの合わない叔母を引き取る話が来て、心優しいbutcherは快諾するが、そうした生活にも嫌気がさして、友達とお見合いダンスパーティに出かける。
パートナーの見つからないbutcherは、同行者に置いてけぼりを喰らって泣いている女の子に同情し、ダンスに誘う。29歳のクララは老けて見える上に大卒の高校教師というイモ女だが、二人はすっかり意気投合。夜遅くまでお喋りした上にキスまで交わし、翌日のデートを約束する。
ところが息子の結婚を望んでいたはずの母は、妹同様、自分が放り出されることを心配して良い顔をせず、友達も遊びの付き合いを強要する。周囲の不同意に心優しいbutcherはデートを放り出そうとするが、意を決して彼女に電話をするところで物語は終わる。
結婚相手の見つからない男女、婚活パーティ、パラサイト、核家族と現代に通用するテーマが目白押しで、日本社会がむしろ当時のアメリカに近づいたのかもしれない。
醜男と醜女という設定の男女を演じるアーネスト・ボーグナインとベッツィ・ブレアは、年齢を除けばごく普通の容姿で若干違和感があるが、「あなたはいい人よ」と訳された台詞が、"You're a good butcher."なのが可笑しい。
劇中、マーティがクララに「母には僕が必要だと言ってきたが、本当はそうじゃない。お父さんを必要としているのは君なんだ。お父さんやお母さんとずっと一緒にいることはできるけれど、一生、君は親離れできないままだ」(I used to think about moving out, you know? And that's what I used to say. "My mother needs me." But when you really get down to it, that ain't it at all. Actually, you need your father. You know what I mean? You're living at home, and you got your father and mother there, and you can go on like that -- being a little girl all your life.)という台詞が本作の核心部分。
親の世話を言い訳にマーティ自身が親離れできないことを自覚し、新しい人生に踏み出そうとする。
マーティはイタリア系で、誰よりもママンが大事、仲間が大切という背景もあるが、マーティの決意の後に予想されるママンや仲間との軋轢は描かれない。本来なら、そこをマーティがどう乗り越えていくかが本題だが、ニューシネマ以前のヒューマンドラマのため、善意を信じるハッピーエンド。
その後が心配ながらも、往年のハリウッド映画の心地よい余韻がいい。カンヌ映画祭パルム・ドール受賞。 (評価:3)

製作国:スペイン
日本公開:1957年1月15日
監督:ラディスラオ・ヴァホダ 脚本:ホセ・マリオ・サンチェス・シルヴァ、ラディスラオ・ヴァホダ 撮影:エンリケ・ゲルネル 音楽:パブロ・ソロサバル
キネマ旬報:8位
大地に広がる空の映像が神の国を映すように美しい
原題は"Marcelino Pan y Vino"(マルセリーノ パンと葡萄酒)。ホセ・マリア・サンチェス・シルバの小説が原作。マルセリーノは主人公の少年の名。
19世紀のスペインの田舎町が舞台。フランシスコ会修道院の前に赤ん坊が捨て子される。12人の修道士が父となり赤ん坊は5歳の悪戯好きな少年となるが、ある日修道院に立ち寄った母子に会い、同い年のマヌエルという末子がいることを聞かされる。自分の母の存在を修道士に訪ねると母は天国にいると言われる。少年は会ったことのないマヌエルとの空想遊びをするが、台所さんと名付けた修道士に巨人がいるから上がらないようにと言われた二階に行く。そこには磔刑のキリスト像があって、少年の空想遊びの相手はこの像となる。食堂のパンとワインを盗んで椅子に座る像に与えると、像が動いてそれを受け取って飲み食いする。少年が像は神だと知ると、像は少年に望みを聞く。すると少年は母に会いたいと答え、椅子に座った像は少年を抱く。それを覗き見した修道士がみんなを呼びに戻ると、像は十字架に戻り、少年は椅子で眠るようにして息を引き取っている。マルセリーノは奇跡の聖人となり、その日は祝祭日となる。
貧しかった時代には、天国に召すことによって人を苦しみから解放してあげる、可哀そうな孤児を天国の母のもとに召してあげることが神の慈悲・恩寵と考えられた。仏教でも似たような話はあり、類話はキリスト教に限らないが、現代の人間主義の感覚からは、受け入れ難いものがある。
この作品を悲しくも美しい宗教物語と肯定するか、安直な救済であるとして否定するかは、観る人の宗教観・人生観による。
12人の修道士たちがやさしく、少年も可愛い。とりわけ、空を写す煽りの映像がモノクロながらも神の国を映すように美しい。アッシジに修道会を開いたフランチェスコには12人の弟子がいて、イエスの弟子も12人。マルセリーノは神から遣わされた聖人と考えれば、フランシスコ会やイエスになぞらえられる。
主題曲は「マルセリーノの唄」として日本でもヒットした。 (評価:2.5)

日本公開:1957年1月15日
監督:ラディスラオ・ヴァホダ 脚本:ホセ・マリオ・サンチェス・シルヴァ、ラディスラオ・ヴァホダ 撮影:エンリケ・ゲルネル 音楽:パブロ・ソロサバル
キネマ旬報:8位
原題は"Marcelino Pan y Vino"(マルセリーノ パンと葡萄酒)。ホセ・マリア・サンチェス・シルバの小説が原作。マルセリーノは主人公の少年の名。
19世紀のスペインの田舎町が舞台。フランシスコ会修道院の前に赤ん坊が捨て子される。12人の修道士が父となり赤ん坊は5歳の悪戯好きな少年となるが、ある日修道院に立ち寄った母子に会い、同い年のマヌエルという末子がいることを聞かされる。自分の母の存在を修道士に訪ねると母は天国にいると言われる。少年は会ったことのないマヌエルとの空想遊びをするが、台所さんと名付けた修道士に巨人がいるから上がらないようにと言われた二階に行く。そこには磔刑のキリスト像があって、少年の空想遊びの相手はこの像となる。食堂のパンとワインを盗んで椅子に座る像に与えると、像が動いてそれを受け取って飲み食いする。少年が像は神だと知ると、像は少年に望みを聞く。すると少年は母に会いたいと答え、椅子に座った像は少年を抱く。それを覗き見した修道士がみんなを呼びに戻ると、像は十字架に戻り、少年は椅子で眠るようにして息を引き取っている。マルセリーノは奇跡の聖人となり、その日は祝祭日となる。
貧しかった時代には、天国に召すことによって人を苦しみから解放してあげる、可哀そうな孤児を天国の母のもとに召してあげることが神の慈悲・恩寵と考えられた。仏教でも似たような話はあり、類話はキリスト教に限らないが、現代の人間主義の感覚からは、受け入れ難いものがある。
この作品を悲しくも美しい宗教物語と肯定するか、安直な救済であるとして否定するかは、観る人の宗教観・人生観による。
12人の修道士たちがやさしく、少年も可愛い。とりわけ、空を写す煽りの映像がモノクロながらも神の国を映すように美しい。アッシジに修道会を開いたフランチェスコには12人の弟子がいて、イエスの弟子も12人。マルセリーノは神から遣わされた聖人と考えれば、フランシスコ会やイエスになぞらえられる。
主題曲は「マルセリーノの唄」として日本でもヒットした。 (評価:2.5)

製作国:アメリカ
日本公開:1955年10月4日
監督:エリア・カザン 製作:エリア・カザン 脚本:ポール・オスボーン 撮影:テッド・マッコード 音楽:レナード・ローゼンマン
キネマ旬報:1位
ゴールデングローブ作品賞
観る側のピューリタニズムが問われる名作?
原作はスタインベックの同名小説。創世記のカインとアベルの挿話を基にした現代の物語で、兄弟はケレイブ(カイン)とアロン(アベル)、父はアダム。この物語はいわば聖書物語で、カインとアベルの挿話に重ねて観るという宗教的態度が必要となる。そうでないと、現代の視点からは著しくリアリティを欠く。
映画の時代設定は1917年で、西部開拓時代が終わって間もない頃のアメリカ。家族、とりわけ父と子の関係、宗教観・倫理観はきっと映画の通りであって、スタインベックが小説を書き映画となった1950年代においても、その考えがアメリカにおいて理解され支持されていたと考えないと、この映画が当時高評価を得た理由がわからない。具体的にはなぜそれほどまでに父との和解が必要なのかと、母の穢れがなぜそれほどまでにショッキングなのかということ。この映画の根底にあるのはピューリタニズムであり、それに感銘できるかどうかが評価のポイントとなる。
映画そのものは非常に真面目であり、良くできてもいる。ジェームス・ディーンに比べて、アブラがもう少し可愛ければと思うのはピューリタニズム的な態度ではない。古き良きアメリカの風景も見どころ。 (評価:2.5)

日本公開:1955年10月4日
監督:エリア・カザン 製作:エリア・カザン 脚本:ポール・オスボーン 撮影:テッド・マッコード 音楽:レナード・ローゼンマン
キネマ旬報:1位
ゴールデングローブ作品賞
原作はスタインベックの同名小説。創世記のカインとアベルの挿話を基にした現代の物語で、兄弟はケレイブ(カイン)とアロン(アベル)、父はアダム。この物語はいわば聖書物語で、カインとアベルの挿話に重ねて観るという宗教的態度が必要となる。そうでないと、現代の視点からは著しくリアリティを欠く。
映画の時代設定は1917年で、西部開拓時代が終わって間もない頃のアメリカ。家族、とりわけ父と子の関係、宗教観・倫理観はきっと映画の通りであって、スタインベックが小説を書き映画となった1950年代においても、その考えがアメリカにおいて理解され支持されていたと考えないと、この映画が当時高評価を得た理由がわからない。具体的にはなぜそれほどまでに父との和解が必要なのかと、母の穢れがなぜそれほどまでにショッキングなのかということ。この映画の根底にあるのはピューリタニズムであり、それに感銘できるかどうかが評価のポイントとなる。
映画そのものは非常に真面目であり、良くできてもいる。ジェームス・ディーンに比べて、アブラがもう少し可愛ければと思うのはピューリタニズム的な態度ではない。古き良きアメリカの風景も見どころ。 (評価:2.5)

夜の騎士道
日本公開:1956年4月22日
監督:ルネ・クレール 製作:アンドレ・ダヴァン(フランス語版)、ジョルジュ・ルロ 脚本:ルネ・クレール 撮影:ロベール・ルフェーヴル、ロベール・ジュイヤール 美術:レオン・バルザック 音楽:ジョルジュ・ヴァン・パリス
原題"Les Grandes Manœuvres"で、大作戦の意。
騎兵隊中尉のプレイボーイ、アルマン(ジェラール・フィリップ)が、大演習を前に難攻不落の美女をモノにするというミッションを仲間内で賭けるというストーリー。
通俗的なストーリーに初めのうちはうんざりするが、パリから都落ちして帽子店を営むバツイチの年増女マリーを演じるミシェル・モルガンの名演もあって、お洒落なラブロマンス映画に仕上がっている。
マリーにはプロポーズを受けているナイスミドルの紳士デュヴェルジェ(ジャン・デサイー)がいて、これに闘争心を燃やしたアルマンはミイラ取りがミイラになってしまう。
一方のマリーは、初めはただの女好きなハンサムとあしらっているうちに、次第にアルマンに引かれるようになり、それを察したデュヴェルジェの求婚を蹴ってしまう。
ところが、賭けの事実を知って侮辱されたと思い、大演習の前日、求婚するアルマンに絶交を言い渡す。諦められないアルマンは、許してくれるなら翌朝、通りに面した二階の窓を開けておいてくれるように頼む。
そしてアルマンたち騎兵隊の行進がマリーの店の前を通るが、果たして? というもので、ルネ・クレールらしい人生の経験を重ねたエスプリのあるラストとなっている。 (評価:2.5)

夏の夜は三たび微笑む
日本公開:1957年2月5日
監督:イングマール・ベルイマン 脚本:イングマール・ベルイマン 撮影:グンナール・フィッシェル 音楽:エリク・ノルドグレン
原題は"Sommarnattens leende"で、「夏の夜の微笑み」の意。劇中では、ラストで3組の男女がハッピーエンドとなり、邦題はそれを意味する。
全体にはライトなコメディ仕立てで、女好きの弁護士には、幼妻と歳の変わらない前妻の息子、元愛人の女優がいる。女優の現在の愛人は伯爵。弁護士と女優はヨリを戻そうとするが、伯爵は「妻は盗られても愛人は渡さない」と反発。一方、伯爵夫人は夫を女優から取り戻そうとしている。弁護士の幼妻と息子も危うい関係で・・・という中で女優の母がみんなを別荘に招待する。それぞれの愛憎と思惑が交錯する中で、利害の一致する女たちが画策し、最後にはそれぞれが収まるところに収まってシャンシャンとなる。
結局、男は女に手玉に取られているだけ、といういかにもベルイマンらしい作品。男とはきれいに別れなければいけない、そうすれば後で利用できる、といった女優の母の味わい深い台詞もあって、肩が凝らずに見られるが、逆にベルイマン作品としては物足りなさも残る。 (評価:2.5)

no image
製作国:イギリス日本公開:1956年3月15日
監督:ローレンス・オリヴィエ 脚本:アラン・デント、ローレンス・オリヴィエ 撮影:オットー・ヘラー 音楽:ウィリアム・ウォルトン
キネマ旬報:4位
原題"Richard Ⅲ"。ウィリアム・シェイクスピアの同名戯曲が原作。 ランカスター家とヨーク家が権力闘争を繰り広げた15世紀薔薇戦争、イングランド王宮が舞台。
ヨーク家勝利によるエドワード4世戴冠式から始まり、王の末弟グロスター公リチャード(ローレンス・オリヴィエ)が王位継承上位の兄クラレンス公ジョージ(ジョン・ギールグッド)、皇太子エドワードや政敵を排除。リチャード三世となって王位に就くが、腹心バッキンガム公(ラルフ・リチャードソン)がランカスター家のリッチモンド伯に寝返り、ボズワースの戦いで討たれるまでが描かれる。
基本的には宮廷劇だが、終盤の戦いにロケシーンがあるのと、全編カラー作品であるというのが見どころ。ストーリー的には謀略の限りを尽くす悪党で不具のリチャードを醜悪に演じるローレンス・オリヴィエの熱演で、ほぼ独り舞台といっていい。
ラストはリッチモンド伯の騎士に囲まれて剣で刺されたリチャードが見得を切って果てるシーンが見どころ。 (評価:2.5)

製作国:イタリア、フランス
日本公開:1958年2月22日
監督:フェデリコ・フェリーニ 製作:ジュゼッペ・コリッツィ 脚本:フェデリコ・フェリーニ、エンニオ・フライアーノ、トゥリオ・ピネッリ 撮影:オテッロ・マルテッリ 音楽:ニーノ・ロータ
キネマ旬報:7位
詐欺師が反省するただの「いい映画」
原題"Il Bidone"で、騙し、ダメな人の意。
三人組で詐欺を働く男が主人公の物語。騙す相手が農民やバラックに住む貧民という、詐欺師としてもクズ人間。三人組の若者には妻がいて、妻は夫の生業を知らないが、一緒に出掛けたパーティで紹介された夫の友人が金の煙草入れを盗むのを見てしまい、青年は堅気になる決意を固める。
主人公の信条は仕事に差し障りがないように家族を持たないこと。そんな彼にも昔に別れた家族がいて、娘と偶然出会った時にその目の前で過去の悪行から警察に逮捕されてしまい、半年間収監される。
出所すると新たなメンバーとタッグを組むが、騙した相手に自分の娘と同じくらいの年齢の小児麻痺の娘がいることを知り、金を返してしまう。帰り道、裏切ったと仲間に崖から突き落とされてしまい息絶える・・・というのがストーリーで、悔恨の『道』のエンディングとは違ったバッドエンドとなる。
教訓的でヒューマンな話だが、半世紀経てば『道』同様に、ただの「いい映画」になってしまうのが残念なところ。主人公にブロデリック・クロフォード。フェリーニの妻、ジュリエッタ・マシーナが青年の妻役で出演。 (評価:2.5)

日本公開:1958年2月22日
監督:フェデリコ・フェリーニ 製作:ジュゼッペ・コリッツィ 脚本:フェデリコ・フェリーニ、エンニオ・フライアーノ、トゥリオ・ピネッリ 撮影:オテッロ・マルテッリ 音楽:ニーノ・ロータ
キネマ旬報:7位
原題"Il Bidone"で、騙し、ダメな人の意。
三人組で詐欺を働く男が主人公の物語。騙す相手が農民やバラックに住む貧民という、詐欺師としてもクズ人間。三人組の若者には妻がいて、妻は夫の生業を知らないが、一緒に出掛けたパーティで紹介された夫の友人が金の煙草入れを盗むのを見てしまい、青年は堅気になる決意を固める。
主人公の信条は仕事に差し障りがないように家族を持たないこと。そんな彼にも昔に別れた家族がいて、娘と偶然出会った時にその目の前で過去の悪行から警察に逮捕されてしまい、半年間収監される。
出所すると新たなメンバーとタッグを組むが、騙した相手に自分の娘と同じくらいの年齢の小児麻痺の娘がいることを知り、金を返してしまう。帰り道、裏切ったと仲間に崖から突き落とされてしまい息絶える・・・というのがストーリーで、悔恨の『道』のエンディングとは違ったバッドエンドとなる。
教訓的でヒューマンな話だが、半世紀経てば『道』同様に、ただの「いい映画」になってしまうのが残念なところ。主人公にブロデリック・クロフォード。フェリーニの妻、ジュリエッタ・マシーナが青年の妻役で出演。 (評価:2.5)

慕情
日本公開:1955年11月18日
監督:ヘンリー・キング 製作:バディ・アドラー 脚本:ジョン・パトリック 撮影:レオン・シャムロイ 音楽:アルフレッド・ニューマン
原題"Love Is a Many-Splendored Thing"で、愛は多くの輝きをもつものの意。ハン・スーインの自伝的小説"A Many-Splendoured Thing"が原作。
第二次世界大戦後、1949年頃の香港が舞台。
ハン・スーイン(ジェニファー・ジョーンズ)は中国人とベルギー人の混血女性だが、本作では中国人とイギリス人の混血になっている。中華民国軍将校の夫が内戦で戦死し寡婦となり、香港の病院に女医として勤務。アメリカ人の特派員マーク(ウィリアム・ホールデン)と恋に落ちるが、朝鮮戦争に従軍して戦死してしまうという悲恋物語。マークは、実話ではオーストラリア人のイアン・モリソンで、シンガポール駐在のタイムズ特派員。
劇中、スーインが自分はEurasianだと説明するが、アジア人とヨーロッパ人の混血のことで、白人社会からも中国人社会からも差別を受ける描写が出てくる。心情的には父方の中国人としての帰属意識が強く大陸志向が強いが、差別やアイデンティティについては掘り下げられず、全体としては未亡人と妻帯者の単なる不倫メロドラマになっている。
見どころは舞台となる香港の景色で、スーインが勤めていたクイーン・メアリー病院は香港島の西にあるが、撮影にはビクトリア・ピークの北にある外国人記者クラブが使われている。二人がデートする美しい浜辺は香港島の南、空撮もあって、当時の香港が楽しめるが、二人の待ち合わせ場所でラストシーンの丘は、香港ではなくカリフォルニアの田舎らしい。
中華人民共和国の建国は1949年10月、中華民国の台湾遷都は同年12月、金日成軍が38度線を越えるのは1950年6月。歴史を頭に入れながら見ると、メロドラマも現代史劇になるが、本作の主役にして最大の功労者は主題曲の"Love Is a Many-Splendored Thing"(慕情)で、さまざまなアレンジでロマンチックなメロディーが全編を流れる。アカデミー賞歌曲賞受賞。歌詞入りの主題歌はナット・キング・コールが歌っている。 (評価:2.5)

ラ・ポワント・クールト
日本公開:2019年12月21日
監督:アニエス・ヴァルダ 脚本:アニエス・ヴァルダ
原題"La Pointe Courte"で、南仏セートにある漁村名。アニエス・ヴァルダの長編デビュー作。
ラ・ポワント・クールトは地中海の潟湖トー湖に面した漁村。この村で生まれたパリに住む男(フィリップ・ノワレ)が浮気をし、バカンスに行くところもなく12年ぶりに故郷に帰ってくる。妻(シルヴィア・モンフォール)も夫に離婚を決意させるために追いかけてくるが、村人たちには散歩して会話ばかりしている奇異なカップルに映る。
一方、ラ・ポワント・クールトではトー湖の水質汚染のために漁が禁止されていて、漁師たちは検査官の目を盗んでムール貝を密漁。若者の1人が捕まって投獄されたり、男にだらしない子沢山の女の子供が病死したり、若者が村の祭りのレガッタ槍試合のために仮釈放されて活躍。恋人の父に結婚を許されるというエピソードが並行して語られる。
そうした中で、パリから来た夫妻の愛についての観念的な会話が続き、妻は結婚を継続することを決意するという内容。
セートはリゾート地で、男女の会話よりも、半世紀前の人々の生活や風物の方が見ていて飽きない。レガッタの槍試合も楽しい。
フォトグラファー出身のアニエス・ヴァルダらしい画面構成や演出が映像的には見どころだが、映画としてはいささか不自然で生硬。観念的な愛についてもわかったようでわからないという、ヌーベルバーグの青臭い空気が漂う作品。
観光映画としては魅力的で、アニエス・ヴァルダが劇映画よりもドキュメンタリーが向いていることを認識させる。 (評価:2.5)

悪魔のような女
日本公開:1955年7月26日
監督:アンリ=ジョルジュ・クルーゾー 脚本:アンリ=ジョルジュ・クルーゾー、ジェローム・ジェロミニ 撮影:アルマン・ティラール、ロベール・ジュイヤール 音楽:ジョルジュ・ヴァン・パリス
原題"Les Diaboliques"で、悪魔のような者の意。ピエール・ボワローとトーマス・ナルスジャックの小説"Celle qui n'était plus"が原作。
寄宿学校校長のミシェル(ポール・ムーリス)を妻で学校オーナーのクリスティーナ(ヴェラ・クルーゾー)と教師でミシェルの愛人ニコール(シモーヌ・シニョレ)が共謀して殺害するというスリラーで、ニコールのアパートの浴槽でミシェルを溺死させ、学校のプールに投げ込んで事故死に見せかける。
ところがプールから死体が失せ、クリーニングされた背広が届くというミステリアスな展開となり、幽霊かはたまた何者かの仕業かという展開となる。
ミシェルはDV夫で、病弱なクリスティーナは離婚を望み、ニコールも別れたがっているという設定。ここまでくればミステリーのおおよその構造は読めてしまうが、アンリ=ジョルジュ・クルーゾーの演出が上手くて、サスペンスというよりはホラーとして最後まで楽しめる作品になっている。
シモーヌ・シニョレの堂々とした悪女ぶりが見どころのスリラーものの古典的な名作だが、クリスティーナが少女のように可憐すぎて行動に不自然さが伴うこと、中盤現れて事件を解決する元刑事フィチェット(シャルル・ヴァネル)が、あたかも事件の真相を知っているかの如くクリスティーナに接触してくるのも気になる。
クリスティーナ役のヴェラ・クルーゾーはアンリ=ジョルジュの妻で、ホテルの浴室で心臓発作を起こして急死していて、本作と微妙に重なるのが因縁くさい。 (評価:2.5)

去り行く男
日本公開:1956年2月25日
監督:デルマー・デイヴィス 製作:ウィリアム・J・ファディマン 脚本:ラッセル・S・ヒューズ、デルマー・デイヴィス 撮影:チャールズ・ロートン・Jr 音楽:デヴィッド・ラクシン モリス・W・ストロフ
原題"Jubal"で、主人公の名。ポール・ウェルマンの小説『Jubal Troop』が原作。
望まぬ出産のために母に疎まれ、少年の頃から放浪を続けているカウボーイ、ジューバル(グレン・フォード)が猛吹雪で行き倒れ、牧場主シェップ(アーネスト・ボーグナイン)に救われるところから物語は始まる。
シェップの妻メイ(ヴァレリー・フレンチ)は粗野な夫を嫌っていて、牧童頭ピンキー(ロッド・スタイガー)と浮気しているが、ハンサムなジューバルの出現で早速乗り換え。しかし人の好いシェップを気に入ったジューバルは誘惑を拒否。ところがピンキーに二人が浮気していると吹き込まれたシェップがジューバルに銃を向け、返討ちに遇うという物語。
それぞれの心理描写が巧みな西部劇というよりは牧場ドラマで、シェップの牧場に漸く落ち着き場所を見い出しながら、心ならずもシェップを射殺し、再び放浪に出るジューバルの苦悩を描く。
牧童仲間から殺人犯として追われるが、ピンキーの策謀だった真実が明らかとなり、恋仲となった安息の地を求めて旅をする宗教グループの娘(フェリシア・ファー)と共に、牧場を後にするシーンで終わる。
結末を描かないラストで、おそらくは娘の家族らと共に、安住の地を探し続けるのであろうという余韻を残す。
シェップは女性心理に疎いとはいえ、やたらに色目を使うメイの浮気性に気づかないというのも不自然で、ピンキーに簡単に騙されてしまうのも情けない。 (評価:2.5)

わんわん物語
日本公開:1956年8月8日
監督:ハミルトン・ラスケ、クライド・ジェロニミ、ウィルフレッド・ジャクソン 製作:ウォルト・ディズニー 脚本:アードマン・ペナー、ジョー・リナルディ、ラルフ・ライト、ドン・ダグラディ 音楽:オリヴァー・ウォーレス
原題"Lady and the Tramp"。レディとトランプは、主人公の雌犬、雄犬の名。
それぞれ、貴婦人と放浪者という意味で、レディはペットショップで買われてきた血統書付きのコッカー・スパニエルの飼い犬、トランプは自由を愛する野良犬という設定になっている。
レディは若夫婦のディア家にもらわれてきて、大事に育てられるが、妻が妊娠したことでディア家内の順位が下がってしまう。夫婦の旅行中に犬嫌いの叔母がベビーシッターとしてやってきて、口輪を嵌めたことからレディは家を飛び出し、トランプに助けてもらって行動を共にすることになる。
一難二難あってレディは家に戻るが、逢いに来たトランプが鼠から赤ん坊を守ろうとして大騒動。誤解した叔母にトランプは野犬管理所に送られてしまうが、近所の犬や帰宅して事情を察知したディア夫妻に助けられる。トランプはレディとともにディア家に飼われ、やがて子犬が産まれてハッピーエンドという物語。
子犬の可愛らしさを強調した仕草など、ディズニーっぽいあざとさが若干気に障るが、オペレッタ風にペギー・リーなどの歌曲も入る楽しいファミリー向けアニメーション。
自由を標榜していたトランプが鑑札をもらって飼い犬となり、マイホームパパとなるラストが何かな~という気はする。 (評価:2.5)

製作国:アメリカ
日本公開:1956年3月14日
監督:ジョシュア・ローガン 製作:フレッド・コールマー 脚本:ダニエル・タラダッシュ 撮影:ジェームズ・ウォン・ハウ 音楽:モリス・W・ストロフ
キネマ旬報:3位
Labor Dayにも拘らず穀物倉庫で働く従業員
原題"Picnic"。ウィリアム・インジの同名戯曲の映画化。
本作で描かれるピクニックはLabor Day(労働者の日)に町中総出で楽しむ大掛かりなイベントで、ゲーム大会やダンス、ミスコンもある。ピクニックが進むうちに意気投合した男女が抜け出して静かに収束していくあたりは野遊びに近い。
この日、大学時代の友人を訪ねてカンザスの小さな町に貧しい若者(ウィリアム・ホールデン)がやってくるというシーンから始まるが、友人の恋人(キム・ノヴァク)が登場してすぐに、この美男美女のラブ・ストーリーだとわかってしまうのが、当時のアメリカ映画らしい。
物語は何のひねりもなく進み、ピクニックのダンスパーティで二人が恋に落ち、駆け落ちするまでが描かれるが、この美女の妹(スーザン・ストラスバーグ)が、本作を多少作品足らしめている。
妹は醜女という設定だが、姉に比べてという程度でスーザン・ストラスバーグは十分可愛い。醜女ゆえに男に持てず、小説家を目指す自立志向の女という設定で、顔はいいが頭は空っぽという姉に、金持ち息子との結婚を望む母親に背いて、風来坊との駆け落ちをけしかける。
それに素直に従う姉は、家族や社会慣習の束縛を離れて、貧しくとも愛に生きるという自由な女を目指すことになるのが、テーマといえばテーマ。
時代性を勘案すればそれなりのテーマだが、出会った翌日には駆け落ちするという、どちらも思慮のない少々おつむの軽い男女のラブストーリーでは、暇潰しにもならず、せいぜいがキム・ノヴァクの美貌を愛でるくらいしかない。
友人の家というのがプラントのような穀物倉庫を所有する資本家なのだが、Labor Dayにも拘らず、倉庫で仕事をしている従業員がいるのがどうにもしっくりこない。 (評価:2)

日本公開:1956年3月14日
監督:ジョシュア・ローガン 製作:フレッド・コールマー 脚本:ダニエル・タラダッシュ 撮影:ジェームズ・ウォン・ハウ 音楽:モリス・W・ストロフ
キネマ旬報:3位
原題"Picnic"。ウィリアム・インジの同名戯曲の映画化。
本作で描かれるピクニックはLabor Day(労働者の日)に町中総出で楽しむ大掛かりなイベントで、ゲーム大会やダンス、ミスコンもある。ピクニックが進むうちに意気投合した男女が抜け出して静かに収束していくあたりは野遊びに近い。
この日、大学時代の友人を訪ねてカンザスの小さな町に貧しい若者(ウィリアム・ホールデン)がやってくるというシーンから始まるが、友人の恋人(キム・ノヴァク)が登場してすぐに、この美男美女のラブ・ストーリーだとわかってしまうのが、当時のアメリカ映画らしい。
物語は何のひねりもなく進み、ピクニックのダンスパーティで二人が恋に落ち、駆け落ちするまでが描かれるが、この美女の妹(スーザン・ストラスバーグ)が、本作を多少作品足らしめている。
妹は醜女という設定だが、姉に比べてという程度でスーザン・ストラスバーグは十分可愛い。醜女ゆえに男に持てず、小説家を目指す自立志向の女という設定で、顔はいいが頭は空っぽという姉に、金持ち息子との結婚を望む母親に背いて、風来坊との駆け落ちをけしかける。
それに素直に従う姉は、家族や社会慣習の束縛を離れて、貧しくとも愛に生きるという自由な女を目指すことになるのが、テーマといえばテーマ。
時代性を勘案すればそれなりのテーマだが、出会った翌日には駆け落ちするという、どちらも思慮のない少々おつむの軽い男女のラブストーリーでは、暇潰しにもならず、せいぜいがキム・ノヴァクの美貌を愛でるくらいしかない。
友人の家というのがプラントのような穀物倉庫を所有する資本家なのだが、Labor Dayにも拘らず、倉庫で仕事をしている従業員がいるのがどうにもしっくりこない。 (評価:2)

製作国:アメリカ
日本公開:1956年3月16日
監督:ウィリアム・ワイラー 製作:ウィリアム・ワイラー 脚本:ジョゼフ・ヘイズ 撮影:リー・ガームス 音楽:ゲイル・クビク
キネマ旬報:2位
ボギーがカッコ良ければストーリーはどうでもいい
原題"The Desperate Hours"で、必死の時間の意。ジョゼフ・ヘイズの同名小説が原作。
アメリカ中西部の町が舞台。会社役員の夫(フレドリック・マーチ)、妻(マーサ・スコット)、娘、息子が暮らす平和な中流家庭に脱獄囚が逃げ込み立て籠もるという物語で、最後には脱獄囚3人は警官隊に射殺され、一家は無事救出される。
どうにも腑に落ちないのが、立て籠もり中に夫は会社に行き、娘はボーイフレンドとデートに行くことで、人質に取られた家族を心配して警察に連絡しないこと。
連絡すれば警察は人質お構いなしに銃撃戦を始めるだろうという前提で、警察は全く信用されていない。
だから自力で家族を守ろうというアメリカ的父親魂がメインテーマで、息子も父親に負けじと男らしくする西部開拓時代のスピリッツ。そんな精神が受けるのか、シナリオは合理的精神には程遠く、父親の奮闘も空回りしているようにしか見えない。
その挙句、結局最後に一家を救ってくれるのが警察で、ならば最初から警察に届ければ良かったじゃんという結末。事件の功労者は救出を求めようとしない一家の危機を忖度してくれたボーイフレンドと警察で、どこが父親魂なんだという内容。最後に脱獄囚に歯向かうシーンで体面を保っているだけ。
父親が匿名で警察に連絡するのも謎で、逃走資金が届くのを待って何日も居座り、父と娘を外出させ、リスクを冒してさっさと逃亡しない脱獄囚も謎。
脱獄囚の頭領をハンフリー・ボガートが演じるというのが本作最大の目玉だが、ボギーがワルカッコ良ければストーリーなどどうでもいいのか? と言いたくなる作品。 (評価:2)

日本公開:1956年3月16日
監督:ウィリアム・ワイラー 製作:ウィリアム・ワイラー 脚本:ジョゼフ・ヘイズ 撮影:リー・ガームス 音楽:ゲイル・クビク
キネマ旬報:2位
原題"The Desperate Hours"で、必死の時間の意。ジョゼフ・ヘイズの同名小説が原作。
アメリカ中西部の町が舞台。会社役員の夫(フレドリック・マーチ)、妻(マーサ・スコット)、娘、息子が暮らす平和な中流家庭に脱獄囚が逃げ込み立て籠もるという物語で、最後には脱獄囚3人は警官隊に射殺され、一家は無事救出される。
どうにも腑に落ちないのが、立て籠もり中に夫は会社に行き、娘はボーイフレンドとデートに行くことで、人質に取られた家族を心配して警察に連絡しないこと。
連絡すれば警察は人質お構いなしに銃撃戦を始めるだろうという前提で、警察は全く信用されていない。
だから自力で家族を守ろうというアメリカ的父親魂がメインテーマで、息子も父親に負けじと男らしくする西部開拓時代のスピリッツ。そんな精神が受けるのか、シナリオは合理的精神には程遠く、父親の奮闘も空回りしているようにしか見えない。
その挙句、結局最後に一家を救ってくれるのが警察で、ならば最初から警察に届ければ良かったじゃんという結末。事件の功労者は救出を求めようとしない一家の危機を忖度してくれたボーイフレンドと警察で、どこが父親魂なんだという内容。最後に脱獄囚に歯向かうシーンで体面を保っているだけ。
父親が匿名で警察に連絡するのも謎で、逃走資金が届くのを待って何日も居座り、父と娘を外出させ、リスクを冒してさっさと逃亡しない脱獄囚も謎。
脱獄囚の頭領をハンフリー・ボガートが演じるというのが本作最大の目玉だが、ボギーがワルカッコ良ければストーリーなどどうでもいいのか? と言いたくなる作品。 (評価:2)

ハリーの災難
日本公開:1956年2月8日
監督:アルフレッド・ヒッチコック 製作:アルフレッド・ヒッチコック 脚本:ジョン・マイケル・ヘイズ 撮影:ロバート・バークス 音楽:バーナード・ハーマン
原題"The Trouble with Harry"で、ハリーとのトラブルの意。ジャック・トレヴァー・ストーリーの同名小説が原作。
山中で死体となって倒れていたハリーを巡るサスペンスコメディで、頭の傷を見て自分が殺してしまったのではないかと思い込んだ村人たちが、死体を隠そうとしてドタバタを演じる。
犯人候補は密猟者(エドモンド・グエン)、子持ちの後妻(シャーリー・マクレーン)、ハイミス(ミルドレッド・ナットウィック)の3人で、これに後妻に惚れている画家(ジョン・フォーサイス)が加わるが、結局死体は殺されたのではなく心臓麻痺だったというオチ。
小劇場の芝居で見るような話で、B級二本立てで見るプログラム・ピクチャーの感じの映画。
特筆すべきは舞台となる村の田園風景の美しさで、色づく秋の景色の中で紅葉した木々が効果的に使われている。死体とは対照的な田園風景の中に殺人騒動を牧歌的に描いているが、サスペンスとしては気の抜けたサイダーを飲んでいるみたいで、喉を刺激するものがない。
ロケ地はバーモント州のカントリーサイド。
シャーリー・マクレーンは、これが映画初出演。 (評価:2)

泥棒成金
日本公開:1955年10月18日
監督:アルフレッド・ヒッチコック 製作:アルフレッド・ヒッチコック 脚本:ジョン・マイケル・ヘイズ 撮影:ロバート・バークス 音楽:リン・マーレイ
原題”To Catch a Thief”で、泥棒を捕まえるためにの意。デヴィッド・ダッジの同名小説が原作。
宝石泥棒ロビー(ケーリー・グラント)が引退して南仏でのんびり暮らしていると、手口をまねた宝石泥棒事件が連続し、警察に拘束されそうになる。そこで自らの潔白を証明するために犯人をお捕まえようとするお話で、真似っこの黒幕(チャールズ・ヴァネル)は元仲間だったというオチ。
最初に情報収集で元仲間が経営するレストランに行き、次に宝石顧客リストを持っている保険屋(ジョン・ウィリアムズ)、元詐欺師の金持ち母娘と巡る。
娘フランセス(グレイス・ケリー)とロビーの恋物語を絡めるが、サスペンスとしては工夫がない上にシナリオが粗雑で、黒幕が泥棒をする動機も不明なら、実行犯の女が命令に従っている理由も不明。黒幕は邪魔なロビーを消そうとするが、消したらロビーが犯人ではないことが明らかとなり、警察の捜査が自分たちに及ぶことも考えないほどに頭が悪い。
一件落着してロビーの名誉は回復されるが、サスペンスとしては不出来、美男美女の恋物語としては退屈で、見どころはグレイス・ケリーの美貌と南仏の美しい風景となっている。
ロビーのニックネームが猫で、忍び足で屋根を渡り、窓から忍び込み、しかも金持ちしか盗らない義賊で、冒頭シーンから鼠小僧の真似っこを思わせるのが受ける。
海岸シーンはモナコでも撮影されていて、本作の公開翌年、グレイス・ケリーがモナコ公妃となり、自動車事故で死んだ場所の近くがロケ地だったという因縁の作品。 (評価:2)

非情の罠
日本公開:1960年9月17日
監督:スタンリー・キューブリック 製作:モリス・ブーゼル 脚本:スタンリー・キューブリック、ハワード・O・サックラー 撮影:スタンリー・キューブリック 音楽:ジェラルド・フリード
キューブリックの初期作品。原題は"Killer's Kiss"で「殺人者のキス」。
邦題も今一つだが、タイトルはやや抽象的。芽が出ずに引退を考えているボクサーの男が、たまたま中庭を挟んだ向かいの窓の美人の窮地を助けたことから恋してしまうという物語。
女はダンスホールで男性客のパートナーを務めるホステスで、ホールを経営するギャングのボスの情婦。二人で主人公の郷里に逃げようとするが、ボスが許すはずもなく主人公と誤ってマネージャーが殺され、女も監禁されてしまう。彼女を助けるために単身乗り込むが、女は主人公を裏切って命乞いをする始末。ギャングと主人公のチェイスが始まり、最後は警察がやってきて一件落着。
主人公が郷里に帰る駅で淡い期待をしていると・・・というハッピーエンドでタイトル同様に凡庸な作品。
アクション映画なので退屈はしないが見るべきところはなく、冒頭の試合でのされる主人公のボクシングシーンと後半逃げ込んだマネキン倉庫の映像が面白いくらいか。撮影も兼務したキューブリックのカメラアングルは結構凝っていて、後の作品での映像へのこだわりの萌芽を見ることができる。
しかし、へなちょことはいえ一応ボクサーなのに、ギャングとの戦いでその片鱗さえもないのは演出的にどうか。
ラストシーンも予定調和で、鬼才キューブリックも昔は凡庸だったと知って、少しだけ親近感を感じさせてくれる。 (評価:2)

理由なき反抗
日本公開:1956年4月18日
監督:ニコラス・レイ 製作:デヴィッド・ワイスバート 脚本:スチュワート・スターン、アーヴィング・シュルマン 撮影:アーネスト・ホーラー 音楽:レナード・ローゼンマン
ジェームズ・ディーンの代表作。原題は"Rebel Without a Cause"で「理由なき反抗者」の意。
60年前の作品とはいえ、設定もシナリオも相当にひどい。反抗期のミドルティーンの無軌道な生態を描くが、少年たちの親や周囲の大人たちの造形に問題がありすぎてリアリティを欠く。つまりシナリオのためのシナリオ。主人公の「理由なき反抗」も決して理由なしとはいえない。
登場するハイスクールの少年少女たちは、どうしようもない不良ばかりで、そんな連中の子供じみた悪行は単なる仲間内の喧嘩で、社会や大人たちに対する反抗ですらなく「理由なき反抗」とさも理由がありそうに描くこと自体が噴飯。
チキンレースで不良の一人が事故死するが、全員が逃げ出すのはともかく、ガールフレンド(ナタリー・ウッド)が悲しみもせずにすぐ後にチキンの相手だったジェームズ・ディーンの代表作と恋をしてしまうという無茶苦茶ぶり。テーマばかりが先行して、登場人物を記号化したチェスの駒のように動かしているだけでは、ミドルティーンの理由なき反抗は描けない。タイトルはかっこいいが内容は名前負けしている。
チキンがひよっこと訳されているのに時代を感じる。 (評価:2)

七年目の浮気
日本公開:1955年11月1日
監督:ビリー・ワイルダー 製作:チャールズ・K・フェルドマン、ビリー・ワイルダー 脚本:ビリー・ワイルダー、ジョージ・アクセルロッド 撮影:ミルトン・クラスナー 音楽:アルフレッド・ニューマン
原題は”The Seven Year Itch”で、七年目の掻痒の意。台詞の字幕では、七年目の痒みと訳されている。ジョージ・アクセルロッドの同名の戯曲が原作。
マリリン・モンロー28歳が、22歳のブロンド美女の役を演じる作品で、地下鉄の送風口の風にスカートが舞い上がるシーンが有名。物語自体は、結婚七年目の中年男が妻子の夏休みの留守中に、共同住宅の階上にやってきたブロンドとの妄想的浮気をするというもので、会社の秘書や女に迫られるという男の妄想ばかりが描かれ、ばかばかしい上に退屈。
モンローを留守宅に招待するも妄想から彼女に迫り、それでもモンローはいい人と言って許してくれる。挙句に塞いでおいた階上の階段の天井板を外してモンローが現れ、冷房の利いた部屋で寝かせてくれと泊まりに来るという実に妄想系男子にとっては都合のいい話で、要は疲れてモテない男たちをやさしくいたわり癒してくれる万人の男の恋人、マリリン・モンローの観客との疑似恋愛、アイドル映画ということ。
撮影時、夫のジョー・ディマジオと上手くいってなかったモンローは精神的に不安定だったとされるが、少女のように可憐で娼婦のように妖艶な女の二面を上手く演じ分けていて、モンローの魅力を再認識することができる。
地下鉄シーンの前に、前年に公開された『大アマゾンの半魚人』(Creature from the Black Lagoon)を映画館で見るシーンが出てきて、内容的なネタも話されるが、当時アメリカでの話題作。
ラフマニノフのピアノ協奏曲2番が音楽に使われているが、作中で意図されるムード音楽というには違和感。監督のビリー・ワイルダーが好きだったのかもしれないが、音楽的センスはアメリカ的通俗で、逆説的にマリリン・モンロー映画に相応しい。 (評価:1.5)

水爆と深海の怪物
日本公開:1958年12月25日
監督:ロバート・ゴードン 製作:チャールズ・H・シニア 脚本:ジョージ・ワーシング・イエーツ、ハル・スミス 撮影:ヘンリー・フリューリッヒ 特撮:レイ・ハリーハウゼン 音楽:ミッシャ・バカライニコフ
原題"It Came from Beneath the Sea"で、それは海の下からやってきたの意。
フィリピン海溝に棲む巨大な蛸が水爆実験の影響で餌がなくなり、船の人間を襲うようになったという設定で、サンフランシスコ湾に来て大暴れするというだけの話。
見どころはレイ・ハリーハウゼンの特撮しかないのだが、蛸だけに海から上がれず、蛸の足で船に抱きついたり金門橋に足を絡ませるくらいで、ゴジラのように上陸して活躍することができず、特撮がウリの割には何とも寂しい。
ストーリーもつまらなければ特撮も蛸の足がクネクネするだけとなれば、見るべきものは何もないのだが、そうした作品にも不思議と見どころはあって、予算不足からか、あるいは腹が減って自分の足を食ったのか、蛸の足が6本しかないのが見どころとなっている。
主人公は、最初に巨大蛸に遭遇した原子力潜水艦の艦長(ケネス・トビー)と海洋生物研究の女博士(フェイス・ドマーグ)で、二人のラブシーンが随所に出てくるという特撮SF映画にあるまじき演出。
主役にしてもらえていない蛸が可哀想な作品になっている。 (評価:1.5)

日本公開:1956年7月10日
監督:クリスチャン=ジャック 製作:アレクサンドル・ムヌーシュキン 脚本:クリスチャン=ジャック、アンリ=ジョルジュ・クルーゾー、ジャン・フェリー、ジェローム・ジェロミニ、ジャック・レミー 撮影:アルマン・ティラール 音楽:ジョルジュ・ヴァン・パリス
キネマ旬報:7位
原題"Si Tous Les Gars Du Monde"。

日本公開:1956年4月18日
監督:ダニエル・マン 製作:ハル・B・ウォリス 脚本:テネシー・ウィリアムズ 撮影:ジェームズ・ウォン・ハウ 音楽:アレックス・ノース
キネマ旬報:10位
原題"The Rose Tattoo"。